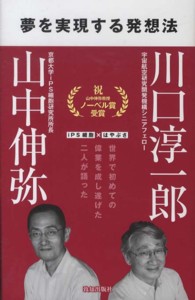内容説明
江戸期から近現代まで、その萌芽から現代の「5万人時代」に至る流れを通観する。江戸と明治の間の断絶、代言人から弁護士へ、戦後の新憲法・新司法制度・弁護士法、臨時司法制度調査会、そして司法制度改革に関する議論・関係法令の制定および施行、そして今後の展望について。なぜか語られなかった弁護士の通史を令和に示す。
目次
はじめに
弁護士制度の原点 繰り返した「二の次」扱い
近代化がもたらした司法・弁護士制度の「特異性・ゆがみ」
「在野」「在朝」奇妙な区分けと格差
初めから圧倒的に少なかった担い手
狭小なまま100年過ごした活動領域・職域
歴史に挑んだ司法制度改革
第1章 「江戸から明治へ」司法の断絶と継続
弁護士の元始をたずねる
江戸時代の司法と裁判
公事宿・公事師とは
開化を焦り過去の全てを切り捨て
探り起こした法実務家の働き
強固に繋がった江戸と明治
第2章 圧縮した近代化の始まり
江藤新平による急進策 代言・代書の公認
訴訟代理─実態は江戸から地続き
難関は裁判所全国配置
法典の整備と法律家の創出
第3章 法律専門職としての制度づくり
代言人規則で免許制に
「官」の監督下に─政治目的はらむ規則改正
弁護士会の祖型が生まれる
私立法律学校の台頭と「在朝」「在野」格差の固定化
代言人、刑事弁護に
第4章 代言人から弁護士へ
立憲政体と法典近代化の完成
代言人20年─高評得た「玉」嘲笑浴びた「石」
自由民権の先頭に立って
第1回帝国議会に弁護士法案
玉石混交を曝け出した混乱
第5章 隆盛期に至る地位の確立
なぜ「弁護士」にしたか
統治機構に根を張り、日本弁護士協会を発足
水平運動に乗り出す
偉才・花形が彩った黄金時代
地位確立の面目躍如 米騒動で全国に出動
隆盛期が産んだ陪審法
第6章 衰微へ向かうなかの「三百」追放
玉石混交から「大家」対「小家」に
臨界点に達した階層分化
東京弁護士会・日本弁護士協会が分裂
昭和恐慌が広げた格差、堕ちる輿望
難航した法案づくり─全面改正の中身
「三百」再考 跳梁跋扈なのか求められたのか
第7章 戦時へ 統制と抑圧に薄れゆく存在
押し流される司法
狭まり失われる居場所
弾圧された抵抗、あげ続けた声
人権蹂躙、総動員政策で調査と告発
自由法曹団と労農弁護士団
粛軍演説・腹切り問答・翼賛会違憲論
「正業に就け」の叱声を浴びて
司法街に焼け残った3棟の会館
第8章 新憲法と新司法制度と新弁護士法
弁護士が法相に 終戦2日後に幕開く新時代
「稀有の脱皮」と呼ばれた法曹一元人事
岩田法相の退場、司法部に起きた内紛
日本国憲法の誕生
2人の弁護士の働き
急ごしらえを強いられた新しい司法
最高裁人事で沸騰した内部衝突
再度の置き去りを越え完全自治を獲る
新弁護士法の概要と日弁連の発足
第9章 臨時司法制度調査会という曲り角
裁判遅延で早々にきしむ司法機構
日弁連の宿題と意識した法曹一元化
臨司は葬儀式場だったのか?
広範な“官製提言”をした意見書
割れた受けとめ─絶対拒否と是々非々と
第10章 政治が揺さ振った司法の独立と弁護士自治
荒れる公判が招いた法廷秩序法
弁護士倫理策定と法廷秩序法改廃をめぐる意見対立
偏向裁判批判から“司法の危機”へ
弁護士界に飛ぶ火の粉
突如出現した弁護人抜き裁判法案
路線を転じた日弁連
第11章 現代型職業像の形成過程
産業経済の成長につれて
中産層が産む法的需要
のびる人権の外延
ほか