- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
現在の物価は適正なのか。これから下がるのか上がるのか。シンプルな問いであっても答えることが難しい物価について、有史以来の変遷を見つめ、その実態と展望を読み解く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
49
SS図書館。農家にとっては、出荷を少し遅らせるだけで、実入りも多くなるくらい、物価上昇のスピードは速い。パリの生活を楽しんでいた市民は窮乏を極め、地方の農家はインフレ長者(65頁)。この間のそこまで言って委員会で竹中平蔵氏は、都市は滅びないというが、インフレの昨今、農村の食糧生産者は強い。江戸時代には、何度も貨幣改鋳してきた。日本経済、令和の貨幣改鋳は円という通貨が未来永劫と思えない中、あり得そうな? あり得なさそうヵ? トランプ氏の就任演説、鶴の一声で決まってしまうのか? 日本経済のレジリエントとは。2025/01/18
鯖
17
フランス革命直前でパンが34倍の価格になり、当時の労働者たちのエンゲル係数は半分がパンとの記述、泣きそう…。おこめ…。江戸時代はコメの価格があがると賃金も上昇したそうで頼むわマジでとなる。この著者、実質賃金も10年単位で上昇する時期に差し掛かってるかもしれないとかこれまでの資産運用の常識があてはまらない時代の到来なのか慎重に見ていく必要があるかもしれないとか、もっときちんと断言してしゃべれや~ってなる。断定を避けるのは筆者の誠実さなのかもしれないが。2025/06/07
エジー@中小企業診断士
9
物価の歴史=モノとカネの関係の歴史を古代バビロニアから中世ヨーロッパ(第1の波)、大航海時代と17世紀の危機(第2の波)、戦乱と革命の18世紀前後(第3の波)、エネルギー価格循環の影響が高まった19世紀後半以降(第4の波)の4期にわたり俯瞰。日本は5章で別記。物価の長期循環が50〜60年周期で発生するコンドラチェフサイクルよりも超長期な波動(200〜300年)も否定できない。人口動態、飢饉、革命、疫病、貿易、戦争などの要因で物価は変動する。中央銀行がインフレを忌避するのは歴史の教訓があるからである。2025/03/11
ぎぃ~
2
超長期の物価循環や20世紀以降の急激なインフレ等興味深い話が多かった。特に足元は生産人口が減少していくため理論的には実質賃金が上がるはずであり、それにより資産価格の頭打ちが起こるならば1970年台からのトマピケティの理論が変わる可能性もあるなぁとこれからの運用方針を考えさせられるいい機会であった。2025/06/26
森野一雨
2
最近の急激な物価高がかなり以前から気になっていたため、読んでみた。題名のとおり、物価の歴史の概観を把握するにはそれなりに有効だが、「今そこにある危機」にどう対処すれば良いかは、この本だけでは分からない。そこまで期待していたわけではないので、仕方がないと言えば仕方のないことなのだが・・・。2025/05/25
-

- 電子書籍
- 大学教育に未来はあるか
-

- 電子書籍
- 家政婦よんだら猫がきた【単話】(3) …
-
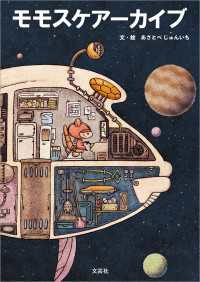
- 電子書籍
- モモスケアーカイブ
-
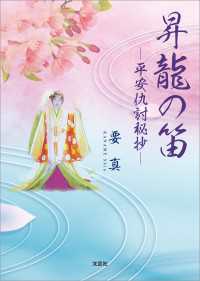
- 電子書籍
- 昇龍の笛 ─平安仇討秘抄─
-

- 電子書籍
- 異世界の姫は俺の雫を搾りたい 【分冊版…




