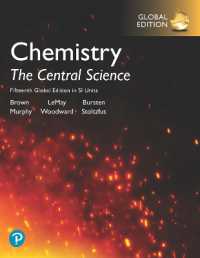- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「給料が上がらず生活が苦しい」という国民の実感と「景気は緩やかに回復している」という政府の発表は食い違っている。テレビや本で紹介される経済学者の言うことは現実問題と関係が無いとすら思える。どうしてデータと実感がズレるのか。GDPや景気動向指数はどのような仕組みなのか。景気の問題と二百年以上向き合ってきた経済学の歴史から、現代の政策に至るまで「景気」の実相を究明し、不透明な日本経済に光をあてる。
目次
はじめに/第1章 「景気」とは何か/「景気」は経済用語か? /経済活動の動向を示す/経済と人体は違う/気分だけで景気は変わらない/鴨長明が見た「景気」/人に見立てた経済に夢を抱く/人は老いるが経済は成長を止めない/人間中心主義への批判/成長のための成長を求める資本主義/ロビンソン・クルーソーなんていない/自分や家族の生活が一大事/人それぞれの景況感/第2章 政府の景気判断は正しいのか/トレンドとサイクル/山あり谷あり/景気動向指数/産業構造の変化を反映/指数の作り方/政府の裁量が入る公式見解/景気循環に神話由来の呼び名/翻弄される政府/「悪くなった」とは言いたくない/景気動向は みづらい? /広がる指標と実態のズレ/第3章 1%成長時代の景況感/GDPは総合成績/人件費込みの粗利益の合計/GDPは企業の目的ではない/儲けを分け合う企業と労働者/外国人観光客もGDPに貢献/持ち家が生む「家賃収入」/名目と実質/成長率に左右される生活実感/景気実感の変遷/年間10%の経済成長/高度成長の要因/成長を支えた設備投資/「バブルの頃は良かった」のか? /失われた30年のはじまり/「景気回復の実感がない」/それでも日本は成長している/まずは1%成長/第4章 経済統計はどう誕生した? /「景気」と向き合ってきた経済学/19世紀初頭に最初の恐慌/産業革命/世界大戦と大恐慌/循環は10年周期という仮説/周期が異なる様々な「循環」/「いずれ不況は均衡に向かう」/仮説や理論で物事を見るクセ/景気動向指数の起源/経済の大きさを測る/GDPで幸福は測れるのか? /政府の意向に沿う統計/GDPの役割と限界/第5章 大不況の中で生まれた経済理論/経済理論は思考実験の道具/レンズの取り扱いに要注意/三人の経済学者/マルクスの問題意識/共産主義社会という夢/労働価値説/資本家の行動で循環する景気/労働者の苦況を映すレンズ/ワルラスの正義論/限界効用理論/価格調整で均衡する市場/労働者と資本家が対等になる世界/「合理的な」理想郷を映すレンズ/パンフレットと大著を遺したケインズ/一般理論/ハッピーエンドを映すレンズ/ワルラスとケインズを使い分け/ケインズの失墜とマルクスの退潮/複雑な現実世界/レンズをはずして見た世界/第6章 袋小路から抜け出すには/染みついた「経済学の思考法」/板挟みの経済学者/あれもこれもは難しい/成果を出せない政府/必要なのは個別の対応/「豊かさ」の捉え方/経済学が見落としてきたもの/アンペイドワーク/コミュニティ/幸福/幸せの損得勘定/幸福は測定できるのか? /仮説と合わない実生活/幸福の経済学/これからの闘い/おわりに/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
koji
まゆまゆ
羊山羊
乱読家 護る会支持!
-
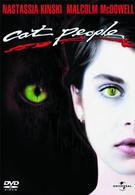
- DVD
- キャット・ピープル