内容説明
アンデス―アマゾンを往復し、出会った、孤独の思考
南米ボリビアで「新しい音楽」として興隆したフォルクローレ。個人の物語を愛し、他者の音を聴かず、堂々と嘘を楽しむ…。共に演奏し、木を伐り、考える中で導かれた、ポスト関係論の人類学。
――「はじめに」より
彼らの人生のテーマを一言だけ取りあげることが許されるならば、それは「孤独」ということになるだろう。音楽家たちは、若い頃、家族にも背を向け、同じフォルクローレ音楽家たち同士の中ですら馴れ合わず、「自分」の探究を続けた。……
本書は、私が三年半にわたり、ボリビアで聞き、時には自分自身もその中に入って経験した、フォルクローレ音楽家たちの物語を記述していくものである。彼らは、ボリビア全体にとっても激動だった時代を、とにかく軽やかに──あるいは軽薄とすらいえるかもしれないほどの軽さで──駆け抜けた。その軽快で、明るい「愛」と「孤独」を書くのが本書の目的である。……
引き込まれる語り口。忘れられない名ゼリフ。驚きの展開。彼らのあまりに巧みな語りっぷりを通じて、普通の人の普通の人生がどれだけ面白いのか、私は見せつけられた思いだった。こうした経験があったので、私は、少しでも彼らの語りに近いものを自分で書いてみたいと思ったのだ。だから、この本は、通読できる民族誌を目指している。……
これまでの人類学にとって、「関係」という概念は揺るぎない重要性を持ってきた。それゆえ、関係以降にあるものを考えるというのは、極めて挑戦的な問いである。本書もまた──それがあまりに大きく、無謀な問いであることは承知の上で──「孤独」の側から人類学理論を刷新していくことを目指している。
音楽家たちが、とんでもなく新しい何かを愛し、目指したのと同じように。
目次
はじめに
序章 孤独とつながりの人類学
1 私たちの孤独と人類学
2 不安の時代の音楽
3 ラテンアメリカの孤独
4 個人誌という方法とその可能性
5 本書の構成
1章 旅の前にあるもの
1 フォルクローレ音楽に出会う
2 フォルクローレ音楽は論じるに値するのか
3 右でも左でもなく
4 それではフォルクローレ音楽とは何なのか
2章 不器用な音楽家たち
1 ラパスというフィールド
2 最初の問いを着想するまで
3 仕事のつながりに参与する
4 ばらばらな音楽家たち
5 在地論理の取り出し方
3章 物語を愛する人々
1 グルーヴから物語へ
2 とあるコンサート制作のアネクドタ
3 アネクドタ的思考
4 人生とその群像
4章 孤独の内に立ち上がる者たち
1 他者の世界を記述すること
2 フォルクローレ音楽家の肩越しに見える世界
3 「孤独」から立ち上がる世界
5章 他者に抗する戦士/旅人
1 フォルクローレ音楽をめぐるノスタルジアとブーム
2 他者に抗うための音楽
3 個が個であるための音楽
4 反抗、世代、強度
6章 「不真面目」なひとりの楽器職人
1 近代の孤独とポスト多文化主義時代の孤独
2 民族誌的背景──アイキレという場所
3 ある女性楽器製作者「モニカ」のアネクドタ
4 すれ違いを笑い飛ばすこと
5 多層なるものとしてのひとり
7章 アマゾンの開拓者
1 アンデスからアマゾンに下る経験
2 カバドールとそのライフヒストリー
3 カバドールへの同行取材
4 カバドールの論理
5 決して交わることのないもの、にわかには知覚できないもの
終章 すでにそこにあるもの
1 関係の彼方へ
2 そのものの内にある力
3 ばらばらの時間の内で繰り返す
4 美を愛する者たち
注
あとがき
初出一覧
参照文献
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
YO)))
いとう・しんご
mirie0908
takao
-

- 電子書籍
- COMIC異世界ハーレム Vol.11…
-
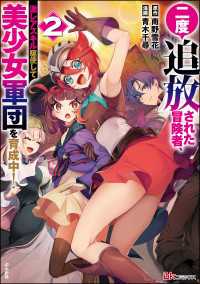
- 電子書籍
- 二度追放された冒険者、激レアスキル駆使…
-
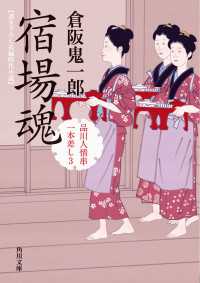
- 電子書籍
- 宿場魂 品川人情串一本差し 3 角川文庫
-
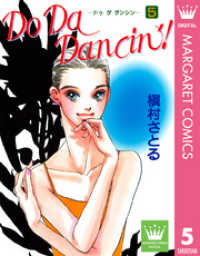
- 電子書籍
- Do Da Dancin’! 5 マー…
-
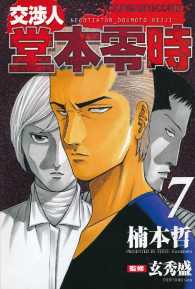
- 電子書籍
- 交渉人 堂本零時 (7)




