- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
私たち人間は、組織をつくることで繁栄を遂げてきた。20世紀に興隆する組織論は、企業組織のあり方の探究などわめて実務的な面をもちつつも、他方で集団を形成し協働するという人間本性に根ざした学際的な学問だ。本書では、バーナード『経営者の役割』やウェーバー『支配について』といった近代組織の基底をなす議論から、リーダーシップ論、組織文化論、組織学習論、意思決定理論、さらにはオライリー&タッシュマン『両利きの経営』といった近年の著作まで国内外の名著30冊を精選。組織に生きるすべての人に向けられた最良のガイド。
目次
はじめに/第1章 組織論の古典/1 チェスター・バーナード『経営者の役割』──組織論ここに始まる/2 ハーバート・サイモン『経営行動』──合理性の限界と組織/3 ジェームズ・マーチ&ハーバート・サイモン『オーガニゼーションズ』──組織研究の統合プログラム/4 リチャード・サイアート&ジェームズ・マーチ『企業の行動理論』──たくさんの小さなアイデア/第2章 近代と組織/5 マックス・ウェーバー『支配について』──組織論のもう一つの源流としての官僚制論/6 佐藤俊樹『近代・組織・資本主義』──近代と組織の不可分性/7 フレデリック・テイラー『科学的管理法』──組織的怠業と科学的タスク設定/8 ピーター・ドラッカー『企業とは何か』──大規模組織のあるべき姿/第3章 合理的システムとしての組織/9 沼上幹『組織デザイン』──分業と調整の現実的デザインに向けて/10 アルフレッド・チャンドラー『組織は戦略に従う』──事業部制組織というイノベーション/11 ジェームズ・トンプソン『行為する組織』──不確実性にどう向き合うか/12 オリバー・ウィリアムソン『市場と企業組織』──組織への取引コスト・アプローチ/第4章 創発的システムとしての組織/13 フリッツ・レスリスバーガー『経営と勤労意欲』──ホーソン研究がもたらした影響/14 フィリップ・セルズニック『組織とリーダーシップ』──経営者の制度的リーダーシップ/15 マーク・グラノヴェター『転職』──ネットワークから埋め込みへ/16 エドガー・シャイン他『DECの興亡』──組織文化のインパクト/17 カール・ワイク『センスメーキングインオーガニゼーションズ』──センスメーキングの手がかりとして/第5章 組織におけるプロセスと人/18 ジェームズ・マーチ&ヨハン・オルセン『組織におけるあいまいさと決定』──ゴミ箱モデルから意思決定を見る/19 マックス・ベイザーマン&ドン・ムーア『行動意思決定論』──ヒューリスティックが招く落とし穴/20 フレデリック・ハーズバーグ『仕事と人間性』──動機づけ要因としての仕事内容/21 ヘンリー・ミンツバーグ『マネジャーの仕事』──マネジャーは何をしているのか/22 ジョセフ・バダラッコ『静かなリーダーシップ』──ヒーローだけがリーダーシップを発揮するのか/23 ロザベス・カンター『企業のなかの男と女』──紅一点はなぜつらいのか/第6章 現実への適用/24 戸部良一他『失敗の本質』──日本の組織は生まれ変わったか/25 服部泰宏『組織行動論の考え方・使い方』──研究と実践の実りある関係に向けて/26 清水剛『感染症と経営』──コロナ禍を忘れないために/第7章 組織の変革とイノベーション/27 ピーター・センゲ『学習する組織』──システム思考を活かす/28 野中郁次郎・竹内弘高『知識創造企業』──知識創造のダイナミクス/29 クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』──ジレンマをもたらす組織的メカニズム/30 チャールズ・オライリー&マイケル・タッシュマン『両利きの経営』──探索と深耕の両立/あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
ぷほは
たむ
ぽん
しまうま
-

- 電子書籍
- 才能なしと言われたおっさんテイマーは、…
-

- 電子書籍
- レベル9の閲覧要員104【タテヨミ】 …
-

- 電子書籍
- 週刊エコノミスト2023年3/21号
-
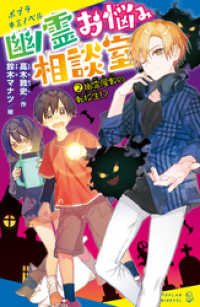
- 電子書籍
- 幽霊お悩み相談室(2) 幽霊屋敷の転校…
-
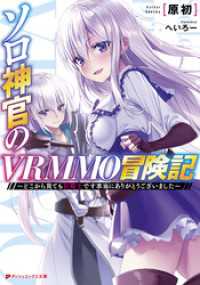
- 電子書籍
- ソロ神官のVRMMO冒険記 ~どこから…




