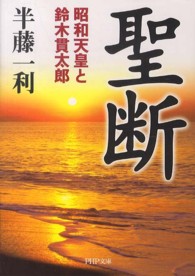内容説明
『暇と退屈の倫理学』『中動態の世界』への刮目すべき挑戦が現れた。
情報社会論より発せられた「庭」と「制作」という提案から私は目を離すことができずにいる。(國分功一郎)
プラットフォーム経済に支配された現代社会。しかし、そこには人間本来の多様性が失われている。
著者は「庭」という概念を通じて、テクノロジーと自然が共生する新たな社会像を提示する。(安宅和人)
*プラットフォーム資本主義と人間との関係はどうあるべきなのか?
ケア、民藝、パターン・ランゲージ、中動態、そして「作庭」。一見無関係なさまざまな分野の知見を総動員してプラットフォームでも、コモンズでもない「庭」と呼ばれるあらたな公共空間のモデルを構想する。『遅いインターネット』から4年、疫病と戦争を経たこの時代にもっとも切実に求められている、情報技術が失わせたものを回復するための智慧がここに。
【目次】
#1 プラットフォームから「庭」へ
#2 「動いている庭」と多自然ガーデニング
#3 「庭」の条件
#4 「ムジナの庭」と事物のコレクティフ
#5 ケアから民藝へ、民藝からパターン・ランゲージへ
#6 「浪費」から「制作」へ
#7 すでに回復されている「中動態の世界」
#8 「家」から「庭」へ
#9 孤独について
#10 コモンズから(プラットフォームではなく)「庭」へ
#11 戦争と一人の女、疫病と一人の男
#12 弱い自立
#13 消費から制作へ
#14 「庭の条件」から「人間の条件」へ
「家」族から国「家」まで、ここしばらく、人類は「家」のことばかりを考えすぎてきたのではないか。しかし人間は「家」だけで暮らしていくのではない。「家庭」という言葉が示すように、そこには「庭」があるのだ。家という関係の絶対性の外部がその暮らしの場に設けられていることが、人間には必要なのではないか。(中略)/「家」の内部で承認の交換を反復するだけでは見えないもの、触れられないものが「庭」という事物と事物の自律的なコミュニケーションが生態系をなす場には渦巻いている。事物そのものへの、問題そのものへのコミュニケーションを取り戻すために、いま、私たちは「庭」を再構築しなければいけないのだ。プラットフォームを「庭」に変えていくことが必要なのだ。(本文より)
目次
#1 プラットフォームから「庭」へ
#2 「動いている庭」と多自然ガーデニング
#3 「庭」の条件
#4 「ムジナの庭」と事物のコレクティフ
#5 ケアから民藝へ、民藝からパターン・ランゲージへ
#6 「浪費」から「制作」へ
#7 すでに回復されている「中動態の世界」
#8 「家」から「庭」へ
#9 孤独について
#10 コモンズから(プラットフォームではなく)「庭」へ
#11 戦争と一人の女、疫病と一人の男
#12 弱い自立
#13 消費から制作へ
#14 「庭の条件」から「人間の条件」へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
逆丸カツハ
特盛
えりまき
ほよじー