内容説明
切断したはずなのに、足のあった場所が痛む…。
世にも奇妙な現象〈幻肢痛〉とつきあいながら、視界の外に広がる世界を思索する4年間の記録。
■白石正明さん(「ケアをひらく」編集者)推薦■
「ない」と「ある」の間には、いまだ名付けられぬ荒野が広がっている。
“幻”と“現”が交錯するそんな幽冥の地を、彼は嬉々として探検する。
その足跡を辿っていくと、私たちもすでに「ない」と「ある」のグラデーションの上にいることに気づいてしまう。
それは端的に気持ちいい。
【内容紹介】
12歳から骨肉腫により人工関節だった著者の青木さんは30歳の時、感染症の罹患を機に太腿から下を切断することを決めます。人工関節ゆえに曲がらない脚、感染症のリスクから切断には前向きでしたが、噂に聞いていた〈幻肢痛〉を身をもって体験することになります。
切断した後の足を火葬して骨壷に入れてもらい、骨壷を眺めながら考えます。
「無いものの存在」に耳を傾けること。
それは例えば、社会の中で抑圧されるマイノリティや、不安に苛まれる人の声と重なるのではないか…。闘病記や当事者研究の書を超えて、自身の痛みに向き合いながら世界を思索する一冊です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
88
満員電車の中で女性の身体に幻肢がめり込んでいく、ってどんな身体感覚なんだろう。そんなイリュージョンを見せてくれる当事者研究。骨腫瘍によって右足切断後に経験した著者が幻肢痛を起点に、身体感覚の変化、義足との関係、そしてアートとの接点を探る画期的な記録である。幻肢痛は「無いものの存在」を感じる現象として捉えられ、身体の不確かさや身体のイメージの変容が語られる。義足は単なる補助具ではなく、身体と物との関係性を再構築する装置として描かれ、自身が仕事として携わるアートはその不確かさに向き合う術として機能する。→2025/07/29
Roko
34
失ったはずの足の痛みを感じることで、その存在を思い出すことがある一方で、失われた聴力に関してはずっと気づかずにいました。「無いものの存在」との関係は、人それぞれだし、誰かに話してわかってもらえるというものでもありません。でも、その存在と共に生き続けることが自分を知ることの一つなのかもしれません。4年に渡る青木さんの日記は、同じようなことを体験するかもしれない誰かにとって、とても貴重なものになるのでしょう。2025/02/04
たっきー
15
30歳で右足を切断した著者が、切断してから4年間足の感覚や状態等を記録したもの。べてるの家の当事者研究を思い出す(実際に参考にされたよう)。それだけではなく、著者の職業が独立型のキュレーターでもあることからのアート視点的な見方、哲学的な見方といろいろな視点があって興味深い。タイトルから福祉・医療関係者が興味をもつことが多そうだが、アート・哲学に関心ある方にも是非読んでほしい。「世の中には自分のルールや客観的な事実だけでは割り切れない当事者にとっての真実がある」。これは専門職が本人よりも本人のことを理解→2025/01/09
よしじ乃輔
14
現代アートに関わる仕事と右足切断という経験を重ね合わせて「無いものの存在」として幻肢痛の思考実験を行った著者の記録。右足を失った後は「幻肢という想像力との共生」と語り、義足を乗り物と捉えてみる柔軟さ。この方しか持ち得ない感性だけれど、医学的な目線だけでは生まれない新しい記録は新鮮でもあり、自ら窮屈な枠に囲い込まなくてもよいとも思えました。2025/01/11
ごまだんご
6
病気で右足を切断することになった方の手記。以前から予定していたもので楽しみですらあったとあり、前半は唯一無二の体験記として読める。当事者としての「障害者」の言及はなるほどと思えた。2025/01/18
-
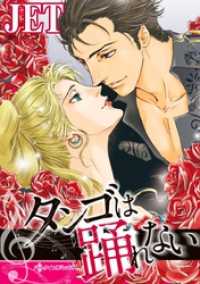
- 電子書籍
- タンゴは踊れない【分冊】 9巻 ハーレ…








