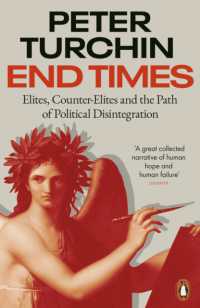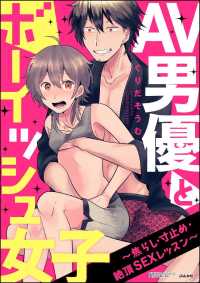内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
薬剤師として,気鋭のEBM研究者として,専門を超えて薬に関する啓蒙活動を行う社会教育者として,蓄積してきた「薬と人間の生活」「薬とその効果」をめぐる科学哲学.エビデンスに基づく科学的合理性を踏まえ,服薬に関する非科学的・非合理的な側面を言語化し,「薬を飲む」「薬が効く」とはどういうことなのか根源的な問いについて思索する
目次
1部 存在 夜空には何が「ある」のか
1章 薬に効果が「ある」といったときの「ある」について
2章 薬剤効果の感覚質
3章 統計世界と生活世界
2部 認識 解釈に対する眼差し、あるいは正当性の論理
4章 情報が表しているもの
5章 メディアとバイアスとスピン
6章 トンデモ医療と正統医療の線引き問題
3部 情動 臨床をめぐる中動態
7章 薬を飲まない・飲めない問題
8章 生活の中の依存と医療
9章 ポリファーマシーを問題にすることの問題
4部 生活 医療と暮らしのはざまで
10章 日常と非日常をめぐる変化の中で
11章 淡い西陽が差し込む午後の病棟で
最終章 「健康」に対する概念的諸連関の展開
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Iwata Kentaro
8
献本御礼。薬を飲むことの「意味」を突き詰めた本としては名郷直樹先生の著作が有名だが、本書もその系列の延長線上にある。ただし、本書は既存の書籍に比べればはるかにセンチメンタルだ。リックにルノーがそう言った如く。2022/08/18
Kyohei Matsumoto
3
薬剤師として仕事をしているから、読んでみた。非常に面白かった。僕と考えていることが似ていると思いながら読んだが、エビデンスを引いてからの哲学的な思索があったからなおさら読んでいて説得感があったなぁと。薬をめぐる様々な哲学的議論が出てきたが、その多くが、もちろん文脈によるが、案外薬はそんなに劇的には効かないという感覚だった。多分これは大学生の頃はよくわからなかったと思うけど、現場にいるとそれは何となく感じる。その中でどうやって仕事をしていくのかは、またゆっくり考えないといけないなと思いながら。2022/02/12
Kenji
1
コロナにしろHPVにしろ、反ワクチン派の意見というのは非科学的なもの、と思い込んでいたが、「肯定することも否定することも、事実の解釈という意味においては同等の営み」とあり、『正しい情報』という情報は実在しないことを知る。『アドヒアランス向上』や『ポリファーマシー対策』は我々が良かれと思って行ってる(求められている)業務だが、「情報によって幸せになれるかは、人それぞれ」であるのだから、患者を批判したり押し付けたりする前にまずはその思いを共有することが肝要であると。。。結局はそれが最も難しいんだよな。2024/05/13
白詰カジキ
1
これを読んでなるほど、そうなのかと感銘を受ける人は医療従事者をやめたほうが良いかもしれない2024/01/09