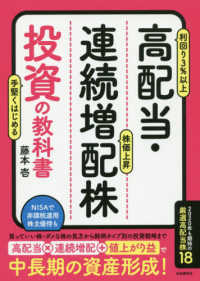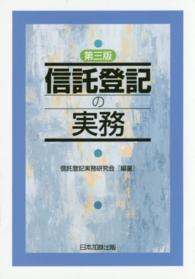内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
1954年に初版刊行以来、数学的思考法の指南書として愛され読み継がれてきたポリア著の『いかにして問題をとくか』は、今日なお様々な問題解決に活用できる普遍的なヒントに満ちています。
本書は、「いかにして問題をとくか」の具体的活用本として、「日常生活にたとえると」、「実際には(ビジネスなどで)どう活用できるのか」という視点から、数多くの身近な問題を取りあげながら解説していきます。『いかにして問題をとくか』を読んで挫折した人も、これからポリアを読もうとしている人にもお薦めしたい一冊です。
目次
まえがき
序 ポリアの問題解決4つのステップ
1 帰納的な発想を用いる
2 定義に帰る
3 背理法(帰謬法)を用いる
4 条件を使いこなしているか
5 図を描いて考える
6 逆向きに考える
7 一般化して考える
8 特殊化して考える
9 類推する
10 兆候から見通す
11 効果的な記号を使う
12 対称性を利用する
13 見直しの勧め
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えも
7
数学的思考法の本なんだけど、思ったよりざっくりしてました。2013/03/20
okanotomokazu
7
激動の時代、先を読むことが難しくなっている。また、グローバル化によって、価値観の異なる人と、対話をする能力が求められている。ここで必要になるのが、「ロジカルな考え方」だ。 本書は、G・ポリアの「いかにして問題をとくか」の入門書。著者は数学者であり、数学教育者の芳沢光雄氏。 長年、数学教育のあり方を模索されてきた芳沢氏だけに、なるべく数式を使わない説明は、面白く、参考になる。親や教師も参考にすべきところが多々ある。特に数学教育は、数学の面白さ、実用性を伝えることが難しい。本書はこの課題にも挑戦している。2012/05/02
麒麟の翼
6
数学は得意な方だと思っているが、かなり難解な印象… 冒頭の『ポリアによる問題解決4つのステップの実践』は、仕事を進めるうえで参考になると思い読み進めたが、理解しづらい部分が多かった。 「6章、逆向きに考える」からは、マークシート方式は解答群を見てから、迷路はゴールからの考え方。 「7章、一般化して考える」からは、一人でも多くの人に納得してもらう努力が大切であること。 「10章、兆候から見通す」からは、論述力を身に付けること。などが参考になった。 仕事で活かすには再読が必要。理解した部分から広げていきたい。2020/12/20
1.3manen
5
1954年に既刊の本を現代的に再生した本。帰納法を重視した発想で、観察や特殊から法則を発見する方法(9ページ)。評者も事例分析から原理原則を見出そうとしてきた経緯があり、共感できる。全体的に、統計学のテキストを読んでいるような感じを受けた。択一式テストへの戒めは、「日本がものごとのプロセスを軽視する国家にならないことを祈るばかり」(50ページ)との指摘は、裏ワザを紹介した後のコメントであり、問題作成者や解答者は肝に銘じるとともに、批判的、創造的思考の評価を大学入試、就職試験に導入しないと、自壊してしまう。2012/09/26
ハルカ
5
数学的な観点から問題へのアプローチを。後半の一部が面倒くさいが、割と当たり前のことが書かれていたりする。多かれ少なかれやっていることであるだけに、どんな時でも意識して出来るようになる、というのが重要なのかも。2012/07/29
-
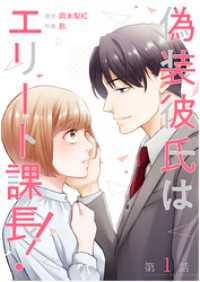
- 電子書籍
- 【単話】偽装彼氏はエリート課長! 第1…


![バナナくん たいそう [実用品] カラープリントパネルシアター](../images/goods/ar2/web/imgdata2/45000/450000887X.jpg)