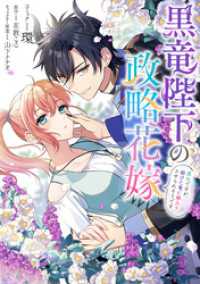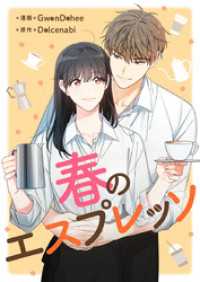内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
従来、数学史の類書は編年体で過去の数学がいかに現代数学に貢献したかを記述するものばかりであった――本書では「数学史」を歴史学の一分野と捉え、過去の数学をその時代の文脈の中で解釈することの重要性を具体的に提示する。数学史とは何か、そして何を目的とするのか、数学史研究の面白さ、数学史研究法の最先端を新鮮な題材と共に紹介する。
目次
第1章 数学:神話と歴史
第2章 数学とは何か、そして数学者とは誰なのか?
第3章 いかにして数学的アイデアは広まるのか?
第4章 数学を学ぶ
第5章 数学者としての生活
第6章 数学内容に入る
第7章 数学史記述法の発展
参考文献
索 引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
6
図書館にて。先日『Oxford数学史』を借りたのだが、検索したときに本書もヒットした。ステドール氏は『Oxford数学史』の編集のひとりである。本書はオックスフォード大学出版局「ベリーショート・イントロダクション」シリーズの一冊(むかしは岩波の「1冊でわかる」シリーズだったなあ)▲数学史の研究法も、19世紀には他の領域同様に〈二次的な説明から古代中世のテクストを学術的に編集し翻訳することへと移っていった。〉特に20世紀初頭は数学者が古代のテクストを現代数学の記法と概念に翻訳した。行き過ぎであった。2022/08/26
takao
1
ふむ2024/11/27
hisaos
1
#積読本減らそうWEEK 数学史というとバビロニアの数学あたりから始まり、19世紀の西洋の数学くらいまでを論じて終わると思いがちだが、この本は数学者とはどんな人か、どう生活していたのかと、数学をする人への視点が強い。名もなき数学学習者の遺した練習帳の話や、ラグランジュ、リヴウィルなど大学数学の教科書で名前を聞いたことのある程度の数学者たちが初期の数学雑誌を作る活動をしていたことなどが取り上げられている。数学の向こうにたしかに人はいることを意識させてくれる。2021/08/07
hryk
0
現代の視点から記述された、少数の数学者しか登場しないこれまでの数学史とは異なる、歴史学としての数学史とはいかなるものなのか、ダイジェスト的に記述した一冊。VSIシリーズだから仕方ないとはいえもっと詳細な文献案内があるとよかった。2021/08/29