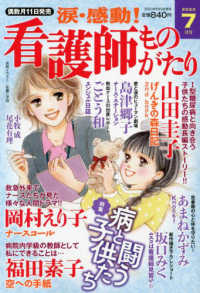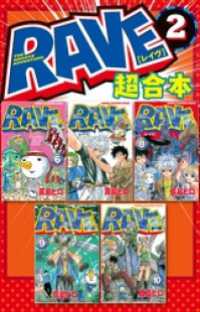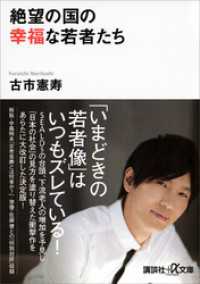内容説明
本書は、ホモ・サピエンスが他の絶滅した化石人類たちとどのように異なるのか、科学者がどのように定義するのかを探り、特に遺伝学の進歩が人類の進化の理解にどのように影響を与えたかを説明する。著者は25年の経験をもとに、人類がアフリカから世界各地に広がり、気候変動に適応し、芸術や技術の革新をもたらした過程を洞窟や岩屋の調査を通じて紹介し、考古学的証拠を使って古代の生活を探る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
10
図書館にて。国立科学博物館の特別展「古代DNA―日本人のきた道― 」のあと、本書を借りた。DNA分析がコモディティ化し、古美術鑑定っぽかった発掘人類学はすっかり警察の科学調査みたくなった▲配偶者選択と近親交配について。氷河期の採集民の骨を鑑定し、血族関係を調べたところ、現代の近親交配タブー(三親等間の結婚をしない)があると分かった(もっとも分析結果では祖父母といとこまでしか得られないが)▲いわゆるビーナス像について。尻と乳房が巨大で丸出しなので、『ふしだらなビーナス』と呼んだことから始まる。そのウェヌスね2025/04/02
takao
2
科学的発見に基づく2024/12/09
Go Extreme
1
氷河期芸術の発見 考古学者の仕事 物質的な証拠 私たちの起源 大きな脳の進化 肉食という解決策 ブロードスペクトラム食 ホモ・サピエンス アフリカ起源 アフリカを出て ネアンデルタール人との交雑 殺す技術 アトラトル ジェネラリスト戦略 寒冷化への適応 氷河期の革新 ソリュートレ文化 マドレーヌ文化 洞窟壁画の世界 思考の世界 豊かな想像力 言語の誕生 儀礼と象徴 新世界 アメリカ大陸へ クローヴィス文化 犬の家畜化 定住と村落 科学が書き換える進化 遺伝子が語る歴史 環境への適応力2025/04/20
Sosseki
0
遺物の痕跡や破片から遺伝子解析や再構築を可能にする技術が人類の起源や進化、生活様式を明らかにしているのに驚く。ホモサピエンスの拡散、寒冷化による絶滅や縮小、狩猟時代にも近親交配を避ける仕組みがあったことには畏敬の念を感じる。専門的なことを大きな抵抗感を感じさせずに読ませるうまさに感服する。作者は農耕・定着が必ずしも優れた「文明」ではないという立場のようで、好感を持てる。2025/02/16