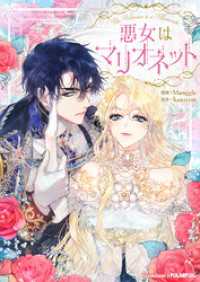内容説明
帝国=アメリカ、ロシア、中国の行動原理を理解するキーワード!
果たして「帝国」は悪なのか? そもそも「帝国」とはいかなる存在なのか?
皇帝がいない国でも「帝国主義」を標榜するとはどういうことか――
それぞれ中国史と英国史を専門に、東西の歴史に通ずる2人の研究者が、
「帝国」をキーワードに世界の近現代史をとらえ直す。
今までになかった新しい視点で、近現代から現代までの歴史の流れを読み解く目を養える。
全編対談のため、充実した内容ながら全編にわたってわかりやすく読み進められる一冊。
【目次】
序章 「帝国」とは何か
第1章 ヨーロッパと中華世界、東西の帝国の邂逅
第2章 押し寄せる列強と東アジア
第3章 ナショナリズムの高まりと帝国の変容
第4章 解体される帝国、生き残る帝国
第5章 アメリカとソ連――新しい二つの帝国の時代
終章 最後にもう一度帝国とは何かを考える
対談を振り返る対談
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
92
近代中国史の岡本教授と英国政治外交史の君塚教授による対談形式で「帝国」をキーワードに近現代史を読み解いていく。「帝国」の定義は微妙にはっきりしない。近代以降に限るとると帝国主義の時代を迎えた19世紀末には世界は帝国で溢れていた。しかし第一次大戦後、ロシア帝国、オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国など名だたる帝国が消滅、さしもの大英帝国でさえ、やがて普通の国に。東洋では清朝も既に崩壊、最後に残った大日本帝国も第二次大戦で消滅、世界で「帝国」を名乗る国は無くなったが「帝国」が無くなったわけではない。⇒2025/02/28
skunk_c
72
対談ものはめったに読まないのだが、岡本・君塚という東西近代史のエース格の学者が、「帝国」という実は意外と定義づけが難しい国家概念を軸に語り合っているというので手に取った。大正解だった。まず帝国について、秦やアッシリアあたりから始め、力尽くで押さえると短命であり、清やオスマンのように多様な民族をゆるやかに統治する(あるいは放置する)形が長命であると押さえる。また、イギリスは国民国家的帝国であったとの押さえ方も腑に落ちた。こうした認識から近現代史を縦横に切っていく。高校必修の「歴史総合」の副読本として最適。2025/04/25
ta_chanko
25
「帝国」とは、様々な民族・文化・宗教などを抱合した広域国家。アッシリアや秦が圧政により短期間で崩壊したことから、アケメネス朝や漢は寛容な統治・支配をおこない、長期間存続。以来、領域内に様々な要素をもつ人々が共存・棲み分けする帝国が歴史上、数多く興亡。しかしフランス革命以降、「民族自決」による「均質な国民」で構成される国民国家が誕生し、産業革命の成果も重なって戦争が総力戦化すると、帝国よりも国民国家が優勢に。国民の生活を豊かにするため、国民国家は軍事力を用いて後進地域に進出し植民地を拡大する「帝国主義」へ。2025/06/11
BLACK無糖好き
20
「帝国」をキーワードに近現代史を振り返る試み。スティーブン・ハウによる古典的な帝国の定義からその実像に入り、近代の国民国家型の帝国への変遷を経て、近年は形の上での帝国は姿を消すも「帝国的なもの」は残り、国民国家との間のせめぎ合いは続いているというのが大枠の流れ。◇帝国が悪で(あらゆる地域で)国民国家が目指すべき健全な国家の姿なのか、今の帝国のイメージで過去の帝国を捉えると実像を見誤る。このへんは重要な指摘。◆このテーマでこの二人が対談して面白くないわけがない。こういう企画はそもそも反則では(笑)。2025/07/27
ピオリーヌ
16
両者とも大好きで本を何冊も読んでいる者なので、二人の対談形式となれば読まずにはいられない!大英帝国と大清帝国の邂逅であるアヘン戦争から現代までの近現代史を辿る内容。現代の中国やロシアは国民国家を形成できず、帝国的にならざるを得ない国(権威主義国家)であり、国民国家と権威主義国家の対立が国際社会の不安定要因となっている。今の中国やロシアを批判するには相手の論理や状況、歴史的背景を分かった上で批判することが大切になる。とても頷ける内容。両者の「人物」を基にした対談を希望!2025/03/06