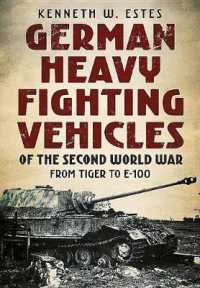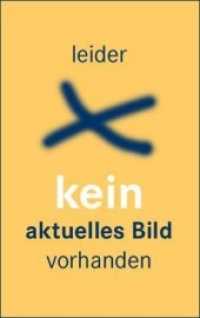内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
「味覚」と「嗜好」は食行動を考えるための『基本』であるが内容は大きく異なる。「味覚」は口腔内での信号の受容と脳への伝達という単純な生理学的現象であるが、一方「嗜好」は食物に対する好悪の判断や長期的な学習・記憶による総合的な判断基準を指す。「おいしさ」は個人の嗜好から生まれる。嗜好の個人差には著しいものがあるが、その要因を整理してみると科学的に捉えることも可能となってくる。本書では「食を考える地平を確立する」ことを目的に、味覚と嗜好から、おいしさに至る感性の世界を生理学・行動学・脳科学・食文化・食品科学などの幅広い視点から解説する。
目次
第1章 味覚と嗜好、そしておいしさ
第2章 味覚と嗅覚・食感
第3章 味覚伝達のメカニズム理論は激変時代
第4章 おいしさを探求する
第5章 油脂は味覚か
第6章 味覚の脳内伝達とやみつきの発生
第7章 食べ物のコクとはなにか
第8章 おいしさの快感と品位
第9章 トウガラシの辛味と痛み;痛みまでがおいしさになる倒錯の世界か?
第10章 伝統の味、だしのおいしさを分析する
第11章 おいしいものは後味がよい
第12章 秋の高級食材、マツタケはなぜ美味しい?
第13章 日本酒のおいしさの科学
第14章 酒のつまみの生理学:ビールのつまみはなぜエダマメやポテトなのか
第15章 ドイツのビールは多飲量性:たくさん飲めるビールはネズミのほうがよくわかる
第16章 魚を生で食べるおいしさ
第17章 新鮮とはどんな味?
第18章 嗜好の教育は幼児から
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はひへほ
ひろ
チクタクマン
ぴこ
ISBN vs ASIN vs OPAC