内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
『プリンキピア』『種の起原』『二重らせん』……タイトルは聞いたことのある科学の名著。では実際には何が書かれ、科学者たちはどのように研究を綴っていたのでしょうか。科学史において重要な書籍を35冊取り上げ、内容に加えて背景や与えた影響も解説。案外知らない名著の内容と、科学史の舞台裏も垣間見える、科学の名著の世界をご案内します。
目次
1章 宇宙と光と革命の始まり(一六~一七世紀)
2章 プリズムと電気と技術の発展(一八世紀)
3章 神と悪魔とエネルギー(一九世紀)
4章 ミクロと時空と宇宙論(二〇世紀前半)
5章 遺伝子と古生物学と人類の進化(二〇世紀後半)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ま
23
僕みたいな愚昧な人間でも、世界は原子で成り立ってることや地球は丸いことなど、昔は専門家でも知らなかったことを常識として知っている。なんだかそのことがとてもありがたいような申し訳なくなるような。「遠くを見ることができたのは、巨人の肩に乗ったからである」byニュートン2021/10/15
田氏
18
読んでいない本について堂々と語る云々な本はまだ読んでいないので堂々と語れないのだが、ここにある35の名著くらいも堂々と語れないようじゃ、1級知ったかぶり士への道は長い。そんな検定はたぶんないが、良質な知ったかぶりをDoするには、いかに的確に要所要所をつまみ食いし、仔細はさておいて全体を俯瞰し、梗概と各ファクターの繋がりを把握するかが肝である。それって突き詰めれば教養と言い換えられる気もするのだ。この世に個々が学び考えることのできるものなど芥子粒ほどもない。ゆえに自覚的に知ったかぶっていきたいのだ。誠実に。2020/06/23
讃壽鐵朗
6
実に要領よくその元となった本の一部を紹介しながら、短い開設の中に歴史上の意義を述べている。まさに私が原書は読まずに科学史を知りたいと思っていたのにぴったしであった。そもそも彼は物理学そのものをやりたかったができないので科学史に移ったというのだが、その方が彼の才能に適していたと言うことだ。2021/03/22
リュウ
4
この本は、16世紀から現代までの科学の歴史をわかりやすく書いた本だ。この本を読むと、昔にはみんなが常識だと思ってたものが、1世紀後には間違った知識として認識されるということがよくあるという部分が興味深かった。例えば、「エーテル」の存在はずっと信じられてきたが、アインシュタインによって完全否定された等である。この本を読んでると、科学は1人で発見するものではなくて、先人が発見したパーツを組みあわせて解いていく物語的な側面もあることがよくわかる。この本は、科学史を理解する上で1度読んで欲しい本である。2021/12/22
Masaru Kamata
3
16世紀に始まる科学革命以後の各分野の発展を、歴史上の科学本を題材にして整理してみせてくれる本。今では常識になっている重要な科学概念や物理量といえども、当初は眉唾物と受け取られていた例が多い。著名な物理学者ですら力とエネルギーを混同していたり、万有引力はオカルトと扱われていたり。しかし、真偽を確かめたい人達の大変な努力で実験と観察が繰り返され、遂にはその正しさが証明されて行くわけで、科学の歴史は先入観や誤った常識、既成勢力との戦いの歴史であった。地球を測った人たちは凄い。2019/10/31
-

- 電子書籍
- 不滅者の終活 第16話 - 第16話 …
-

- 電子書籍
- シャーリー 私を守る君を、守りたいから…
-
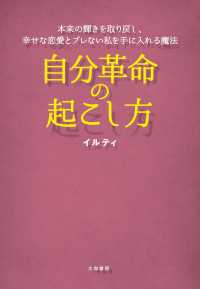
- 電子書籍
- 自分革命の起こし方~本来の輝きを取り戻…
-

- 電子書籍
- スイートハウス 設計事務所物語 1
-
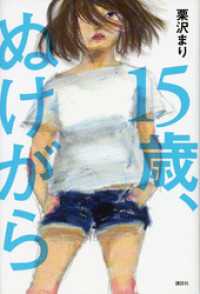
- 電子書籍
- 15歳、ぬけがら




