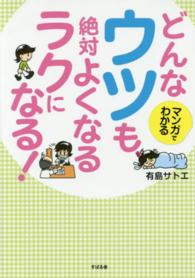内容説明
告知、療養環境の選択、何かを遺すこと、お迎え体験――在宅緩和ケアを受け、自宅で最期を迎えたがん患者たちの語りから、「自らの死を予見しつつ今このときを生きる」という、「日常の生」と地続きにある「死にゆく過程の生」を描き出す。
目次
序章 現代社会においてなぜ死が問題になるのか
1 焦点としての「死にゆく過程」
2 病院死の時代
3 「死にゆく過程」の発見
4 死の問題の現代的位相
5 「死にゆく過程」の社会学へ
第1章 「良い死」の実現――ホスピス・緩和ケアの可能性と困難
1 近代ホスピス運動の誕生
2 ホスピス・緩和ケアの日本的展開
3 誰のための「良い死」か
4 在宅緩和ケアの可能性
5 施設と在宅の二分法を超えて
第2章 未決の問いとしてのがん告知
1 日本におけるがん告知
2 在宅がん患者の告知体験の語り
3 告知後のケアを考える
4 「個人誌の断絶」を生きる困難
第3章 治療を「あきらめる」経験の語り――死にゆく過程における自己の多元性
1 あるがん患者の生活史
2 困難な意思決定への直面
3 一つの生と複数の自己
4 「死にゆく過程」と生の豊かさ
第4章 受け継がれていく生――死にゆく者と看取る者との関係の継続
1 終末期ケア・死別ケアにおける継承性へのアプローチ
2 「受け継がれない意思」とどう向き合うか
3 多様な継承関係へ
第5章 死者との邂逅――終末期体験としての「お迎え」
1 死の臨床とお迎え体験
2 「お迎え」の意味するもの――文化的な死と生物学的な死
3 お迎え体験の実相――誰が迎えに来るのか
4 お迎え体験をどう理解すべきか
5 終末期体験の「ノーマル化」に向けて
終章 死にゆく過程をどう生きるか
1 死にゆく過程を捉える三つの視点
2 決定と非決定のあいだを生きる
補論1 地域社会におけるホスピス運動の形成と展開
1 市民運動としてのホスピス運動
2 近代ホスピス運動の歴史と日本のホスピス
3 調査の方法と対象
4 三つのホスピス運動の形成と展開
5 三つの「理念」の競合
6 結びに代えて
補論2 ホスピスボランティアの意義と可能性
1 新しいボランティア像
2 参加型福祉社会論と「ボランティアのとり込み化」
3 ホスピスボランティアの世界
4 社交としてのボランティア
5 結びに代えて
注
あとがき
文献
事項索引
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たろーたん
Schuhschnabel