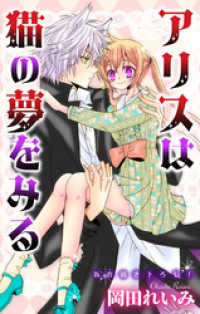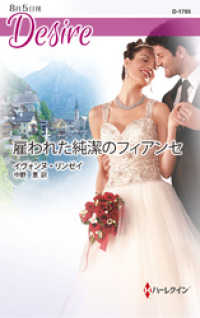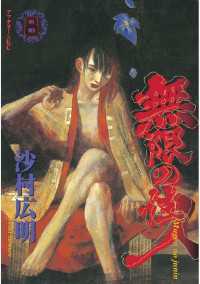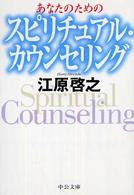内容説明
なぜ「個性」は人々を惹きつける社会的テーマとなったのか。日本社会は「個性」にどんな理想=幻想を思い描いてきたのか。大正期に教育的価値として「個性」が浮上し最初のブームが起こったあと、1980年代に再ブームが到来。『窓ぎわのトットちゃん』のヒットもあり、臨時教育審議会で「個性化教育」路線が推進される。そして社会的価値として定着したこの言葉は、現在も「障害も個性」のような言説によって論争のタネであり続けている。日本の公教育の歩みに即しつつ、「個性」概念の来歴を振り返る。
目次
序章 歴史の中の「個性」/盗癖も「個性」/「鳥の眼」のアプローチ/本書の分析視角/各章の構成/第1章 教育的価値としての浮上──大正新教育と「個性教育」/1 「個性教育」の時代/背景としての「新教育」/大正新教育と「個性教育」/一斉教授法の誕生/集団的効率と個人的疎外/2 成城小学校とドルトン・プラン/澤柳政太郎/成城小学校の創設/ドルトン・プランとは/ドルトン・プランの挫折/「個性教育」とは何だったのか/第2章 個人性を可視化する──「個性調査」の地平/1 「個性尊重」訓令/教育政策への「個性」の取り込み/背景としての入学難問題/「個性調査」/2 近代学校と〈表簿の実践〉/表簿を介しての個人把握/フーコーの試験論/表簿の個人化/カードという技法/3 分析の対象としての個人/心理測定技術との結合/日本の心理学者たち/「個性」はいかに把握されたか/さまざまな「個性」/「個性」の生産/ブームの退潮/第3章 二度目のブーム──臨教審と「個性重視の原則」/1 トットちゃんのユートピア/『窓ぎわのトットちゃん』/小林宗作と大正新教育/トモエ学園の授業スタイル/感性だけの新教育リバイバル/2 閉塞する学校教育/背景としての学校荒廃/「社会問題」による「現実」の強化/学校不信の背景/学校教育の第二の完成期/3 教育改革の時代/臨時教育審議会/原型としての「教育の自由化」論/「個性」の多義的用法による混乱/「尊重」と「重視」の間/第4章 「個性化」の誘惑──差異化のレトリック/1 消費社会の中の「個性」/『なんとなく、クリスタル』/ボードリヤールの消費社会論/強迫観念化する「個性」/2 学校で「個性」はどう教えられてきたのか/学校カリキュラムとしての「個性」/道徳教育の沿革と学習指導要領/道徳カリキュラムの中の「個性」①──中学校の場合/道徳カリキュラムの中の「個性」②──小学校の場合/生徒の自己課題としての「個性の伸長」/どうやって伸ばすのか/「輝く個性」/「個性」は教えられるのか/第5章 実践からレトリックへ──語彙論的考察/1 「個性」の意味変容と二度のピーク/individualityからの乖離/データとしての図書タイトル/「個性」流通の二度のピーク/教育実践からレトリックへ/2 派生語の展開──「個性的」「個性化」「個性派」/レトリックとしての「個性」/派生語1──「個性的」/派生語2──「個性化」/派生語3──「個性派」/「新教育」の社会的帰結/第6章 障害と「個性」──包摂のレトリック/1 「障害も個性」への共感と反発/『五体不満足』と「個性」/『障害者白書』の波紋/障害個性言説の論理的陥穽/共感の底堅さ/「障害は個性」のアンビバレンス/「個性」はなぜ人々を苛立たせるのか/2 「個性の延長」としての発達障害/発達障害とは/「医療化」のプロセス/発達障害と「個性」の親和的関係/「包摂」と「差異化」の間/終章 「個性」のゆくえ/近代化の反作用/価値としての自立/ポスト近代の「個性」/文献一覧/あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zunzun
Go Extreme
Go Extreme
昌也