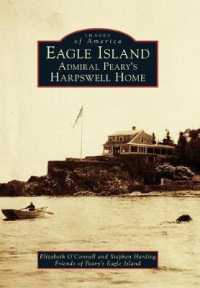内容説明
少子高齢化に消滅自治体、東日本大震災やコロナ禍に象徴される自然災害の数々。
大きく変わりつつあるわが国の姿を背景に、いま、観光そのものも多様化し、変容しつつあると言われて久しい。
転換点にある観光の姿を「観光」「リゾート」「オルタナティブ・ツーリズム」の視点から見直したとき、
都市にできること、農山魚村にできること、それぞれの地域のめざすべきあり方が見えてくる──。
オーバーツーリズム問題やIRの可能性、グリーンツーリズム、ワーケーションやブリージャーなど、
近年の大きな話題を深く理解するために、基礎知識編、歴史編、展開編に加えて、今後の課題と方向性を提示。
多数の図表や事例を用いて具体的に語り、主要出来事年表も備えた、これからの観光に携わるすべてのひとのための教科書。
目次
はじめに
基礎知識編
第一章 今なぜ観光か?
第二章 観光の概念の拡がり
歴史編
第三章 近世以前の観光日本史
第四章 近代の観光日本史
第五章 戦後の観光日本史
展開編
第六章 都市でのオルタナティブ・ツーリズムの展開
第七章 農山漁村でのオルタナティブ・ツーリズムの展開
今後の課題と方向性編
第八章 持続可能な観光振興に向けての課題と方向性
年表/参考文献
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
43
観光は、広い概念である。まちづくりの新しい価値。つまり、観光まちづくりの時代である。さほど有名でない地域にも、結構、円安効果のインバウンドはあった。例えば、木曾路だが、妻籠や馬籠にとどまらず、木曾路全体を満喫する人も出てきたからだ。私の専門からすると、第7章が参考になる(農山漁村でのオルタナティブ・ツーリズムの展開、183頁~)。日本型グリーン・ツーリズム(GT、これについては、『農業経済研究』第96巻第3号の徳島県の事例分析を検討したい)2025/07/04
あきあかね
9
本書は、「観光」という言葉の概念や定義からはじまり、近世以前、近代、戦後の日本の観光の歴史を丹念に追っている。 「観光」を、物見遊山的な「狭義の観光」、保養を目的とした「リゾート」、近年注目される「オルタナティブ・ツーリズム」に区分し、特に、「現代とは異なる価値観を持つ」という意味の「オルタナティブ・ツーリズム」に多くの紙幅を割いている。角館や津和野、川越のように、地域固有の文化や生活を観光資源化することで人びとを惹きつけるタウンツーリズムや、滞在型市民農園の先駆けである松本市の坊主山クラインガルテン等⇒2025/05/21
Go Extreme
1
人口動態:都市集中 地方過疎 高齢化問題 生産年齢人口減少 商店街衰退 観光と地域振興:観光基本法 観光立国推進 外国人観光客 地域資源活用 持続可能観光 オルタナティブ・ツーリズム:グリーンツーリズム 体験型観光 地域文化振興 住民交流 環境配慮 過疎地域:自立促進法 農山漁村衰退 人口減少対策 観光マーケティング 資源活用 観光政策と課題:オーバーツーリズム 交通インフラ整備 環境認証制度 観光まちづくり 歴史と観光発展:温泉巡礼地 リゾート開発 交通網拡充 ディスカバージャパン 戦後経済成長2025/03/12