- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「リーダーシップを発揮するには、組織内でその根拠となる何らかの『権限』が必要だ」と考える人は多いだろう。本書で紹介するのは、そういった権限の有無や強弱によらず、参加する人すべてが発揮する新しいリーダーシップだ。このリーダーシップは具体的スキルとなる「目標設定・共有」「率先垂範」「相互支援」の最小3要素が過不足なく機能することで実現可能となる。個々人のキャリアアップに結びつく一方で、柔らかく強い組織づくりにもつながる「権限によらないリーダーシップ」が支持される理由と習得法、実践法を紹介する。
目次
はじめに 「権限によらないリーダーシップ」が注目を浴びている! /そもそもリーダーシップとは? /20世紀型のリーダーシップが通用しなくなってきた/日本企業も注目し始めた「権限によらないリーダーシップ」とは? /すでに権限を持っている人からのニーズが増えてきたその理由/具体的スキルである最小3要素とは? /なぜ「権限によらないリーダーシップ」という言葉を使うのか? /コミュニケーション力やフォロワーシップとの違い/「権限によらないリーダーシップ」の実践はライフスキルになり得る/第1章 今なぜ、必要なのか/求められる5つの要因/◇要因1◇ 冷戦終結以降、世界は予測不可能な時代に突入したこと/VUCAの時代到来/トップダウン型では時代の激変に対応しきれなくなってきた/◇要因2◇ 激化する競争の中、イノベーションの促進が不可欠になったこと/イノベーション研究での興味深い結果/ボトムアップ型のイノベーションの裏に最小3要素あり/◇要因3◇ 組織のスリム化によるプレイングマネジャーの急増/20世紀型のリーダーシップの限界/◇要因4◇ パワハラ、セクハラへの監視が厳しくなったこと/指示・命令とパワハラの境界があいまいに/「コーチング」との違い/◇要因5◇ 「自己決定」を重視するミレニアル世代やZ世代の出現/「権限を使うと嫌われる」と悩む上司たち/「権限によらないリーダーシップ」は、ミレニアル世代やZ世代と相性がいい/トップダウン型のリーダーシップの限界/第2章 組織をどう変えるか/「権限によらないリーダーシップ」とは? /うまく機能させる鉄則は、最小3要素の徹底/不測の事態においては、実践されやすい/知らず知らずにあなたも発揮している/「権限によらないリーダーシップ=権限をなくす・減らす」ではない/成果志向×心理的安全性から見た組織の4タイプ/学習する組織ではイノベーションが起こりやすい/あなたの職場はどのタイプ? /学習する組織に変化していくには…… /第3章 身につけるために必要なこと/機能するために不可欠な3要素/あなたのまわりの「事例探し」をしてみよう/目標設定・共有は、他の2要素より早い段階で起こるとは限らない/3要素はひとつでも欠けると、うまく機能しなくなる/最小3要素は権限者のリーダーシップでも効果的/メンバーで共有できる目標を見つける難しさ/身の回りの「解決したいこと」をまず目標として設定する/「全体に貢献する」という要素は必要/「目標共有」で重要なのは、言語にして伝えること/目標への納得感が、達成に向けての原動力になる/否定派には、「感情」にある程度寄り添うことが必要/相手が否定する「理由」に向き合い、それを軽減していく/「根回し」で否定派の発生を最小限に抑える/「根回し」で外していけない2つのポイント/根回しでは「質問」が効果的/最初から「全員参加&発揮」を目指さなくてもいい/「取引」で無理やり巻き込もうとしない/ゴール設定を時々見直し、必要ならばアップデートする/大目標にたどり着くための小目標をいくつか設定する/率先垂範は「一人」ではなく「仲間」と一緒に行う/バディを持つ2つのメリット/支援するだけでなく、堂々と支援もされる/第4章 その実践(1)/最初は「バディ」と二人三脚で取り組む/バディは「対等な関係」が大前提/健全なフィードバックには心理的安全性が必須/社内の横の関係でバディをつくった例/まずは社外で「練習」するのもアリ/誰もがいつでも入ってこられるようにオープンにする/制度化された「バディづくり」は失敗の元/求められるのは「自発性」/バディと最初に取り組むのは、「小さな成果」づくり/成果にはお互いへのフィードバックが欠かせない/フィードバックは「ダメ出し」ではない/フィードバックは必ず「S・B・I」の3つを盛り込む/慣れないうちは、ポジティブなフィードバックのみにする/ネガティブなフィードバックでは「改善案」を伝える/ハンバーガー・フィードバックの落とし穴/フィードバックをもらうコツ/ダメ出しを上手に受け取るテクニック/フィードバックの授受が上手になったら、バディづくりは卒業/第5章 その実践(2)【権限者の場合】/部下たちがリーダーシップを発揮しやすい環境をつくる/部下の中からリーダーシップを発揮できそうな人を見つける/「心理的安全性の確保」が必須条件/黒子に徹して細やかに支援をしていく/上と下とを取り持つ「仲介役」を担う/「部下が失敗したときにどう振舞ったか」が見られている/自分からフィードバックを取りにいき、改善する姿勢を見せる/自分のフィードバックが「ダメ出し」になっていないかを定期的にチェック/リーダーシップの発揮が報われる環境をつくる/さらに学びたい人へ/おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
メタボン
タカナとダイアローグ
zunzun
お抹茶
izumone
-

- 電子書籍
- 銀河に落ちた君を求めて 第37話 陰謀…
-
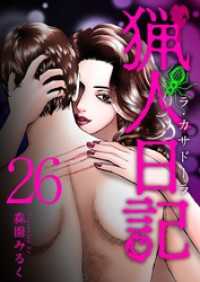
- 電子書籍
- 猟人日記 ラ・カサドーラ 26巻 Th…
-
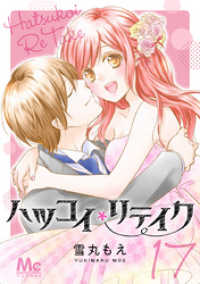
- 電子書籍
- ハツコイリテイク 17 マーガレットコ…
-

- 電子書籍
- 知らなきゃ困る!税理士業務のための民法…
-
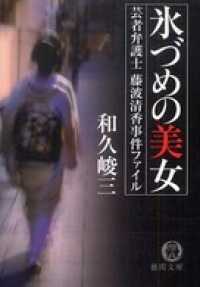
- 電子書籍
- 氷づめの美女 芸者弁護士藤波清香事件フ…




