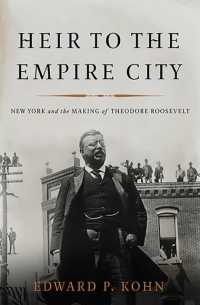内容説明
華々しい戦史も、将軍たちの勇壮な逸話も、ましてや必勝の極意もない小さな兵法書は、なぜ2400年にわたる世界史的ベストセラーになりえたのか?
曹操、蒋介石、毛沢東、山鹿素行、吉田松陰、旧陸海軍、公安警察、労働組合、電通、そしてイギリス軍やアメリカ軍へと読み継がれてきた歴史を辿りつつ、形篇や勢篇、行軍篇など実際のテキストを吟味し、その「魅力」の源泉に迫る!
【目次】
はじめに
中国王朝名一覧
■第一部 書物の旅路ーー不敗への欲望
第一章 戦いの言語化ーー『孫子』の原型
第二章 成立と伝承
第三章 日本の『孫子』ーー江戸時代末期まで
第四章 帝国と冷戦のもとで
■第二部 作品世界を読むーー辞は珠玉の如し
第一章 帝王のためにーー『群書治要』巻三三より
第二章 形と勢ーー永禄三年の読み
第三章 不確定であれーー銀雀山漢墓出土竹簡「奇正」
第四章 集団と自然条件ーー西夏語訳『孫子』より
おわりに
参考文献
学術文庫版へのあとがき
【本書の主なトピック】
□『孫子』古典化の秘密は非万能・抽象・非戦志向にあり
□日清・日露戦争の勝利で進んだ『孫子』の聖典化
□米軍を『孫子』研究に向かわせた毛沢東率いる人民解放軍の脅威
□電通PRセンター初代社長が仕掛けた企業経営者向け『孫子』キャンペーン
□帝王・皇族は『孫子』から何を学んだのかーー『群書治要』
□なぜ勝ち負けが生ずるのかーー形篇・勢篇
□無限に変化し、不確定であれーー銀雀山漢墓出土竹簡「奇正」
□”China Rising”で『孫子』は21世紀世界の必読書へ
目次
はじめに
中国王朝名一覧
■第一部 書物の旅路ーー不敗への欲望
第一章 戦いの言語化ーー『孫子』の原型
第二章 成立と伝承
第三章 日本の『孫子』ーー江戸時代末期まで
第四章 帝国と冷戦のもとで
■第二部 作品世界を読むーー辞は珠玉の如し
第一章 帝王のためにーー『群書治要』巻三三より
第二章 形と勢ーー永禄三年の読み
第三章 不確定であれーー銀雀山漢墓出土竹簡「奇正」
第四章 集団と自然条件ーー西夏語訳『孫子』より
おわりに
参考文献
学術文庫版へのあとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
電羊齋
やす
さとうしん
えふのらん
てっき
-
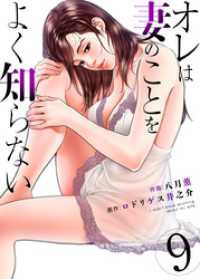
- 電子書籍
- オレは妻のことをよく知らない 9 ゼッ…
-
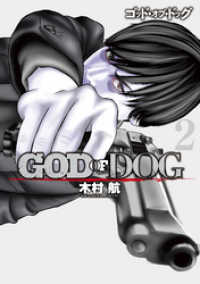
- 電子書籍
- GOD OF DOG(2)