内容説明
エンディングノートや終活への着目は、生前に自身の葬儀などに関心を持つ人々の増加を示しているが、ライフスタイルの変化から「葬儀は不要/シンプルに」という志向も支持を集めている。葬儀は、いつの間にか人々の志向に応じて変えられると見なされるようになった。
いまでこそ葬祭業はサービス業だと思われているが、戦後の葬祭業界は「人の不幸でお金をとる」と長らく批判され、また遺体を扱う事業として蔑視されてきた。葬祭業者たちは、批判に対応して自身の仕事をどう意味づけ、葬儀をサービス業として成立させたのか。
行政との綱引き、消費者・顧客としての遺族との関係、宗教者や地域住民との連携・軋轢――葬儀を商品化した葬祭業者の葛藤の歩みを追い、フィールドワークから葬祭業者自身の職業観も聞き取って、葬祭業の戦後史と私たちの死生観の変容を描き出す。
目次
序章 葬祭事業者にとっての終活ブームとケア
1 終活ブームにおける葬儀
2 職業上、死にかかわること――ケアと商品
3 本書の構成
第1章 葬儀サービスを捉えるために
1 商品化・消費社会での死
2 葬儀サービスでの消費者との相互行為とその特性について
3 死を商業的に扱うことによるジレンマ
4 葬祭業者の感情的不協和と職業イメージ
5 葬祭業から見る近代化
第2章 戦後の葬祭業界の変動要因
1 戦後の経済成長と人口の変化
2 戦後の葬祭業界
3 行政的な主導と葬儀の経済・文化的価値――一九四五―六〇年代
4 マナーの消費と葬儀サービスの開発――一九七〇―八〇年代
5 「心」の時代の葬儀――一九九〇―二〇一〇年代
6 リスク消費としての終活ブーム――二〇一〇年代以降
第3章 商品としての儀礼空間――景観と住空間から排除された死
1 葬儀場所の変化
2 死の排除をめぐる「景観」というレトリック
3 葬儀会館の商品価値
4 人々の視線と行為を意識した死の管理
第4章 葬祭業教育と遺族へのかかわり
1 一九八〇年代の葬祭業者たちが感じた職業イメージ
2 身体の意識化
3 企業教育での利他的側面と商業的側面
4 地域のなかでのグリーフケア
終章 葬祭事業という死のリアリティ
1 商品化された/商品的ではない死
2 生前から死後の準備を推進する――「ライフエンディング」とは
3 「死」から「生」のなかのリスクへ
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
kenitirokikuti
takao
-

- 電子書籍
- 陰キャの僕に罰ゲームで告白してきたはず…
-

- 電子書籍
- 拾ったのが本当に猫かは疑わしい2 アル…
-
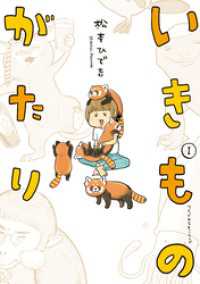
- 電子書籍
- いきものがたり(1)
-
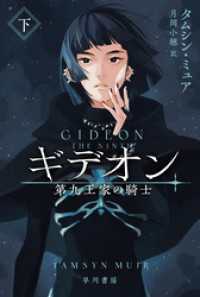
- 電子書籍
- ギデオン 第九王家の騎士 下 ハヤカワ…
-
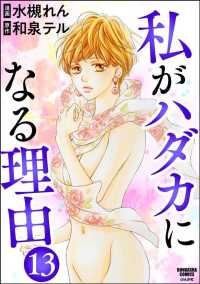
- 電子書籍
- 私がハダカになる理由(分冊版) 【第1…




