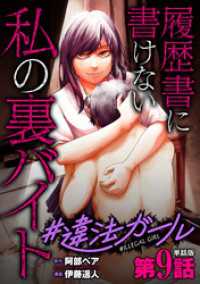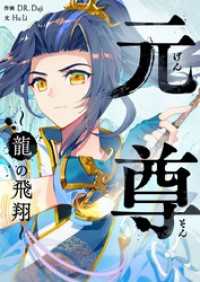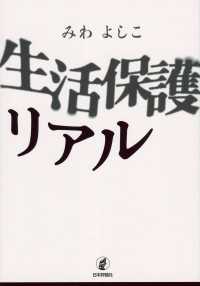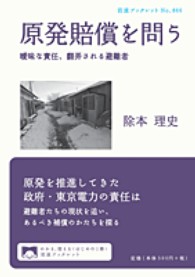内容説明
【軍を見れば、その国の戦略と文化の関係がわかる】
各国の軍事制度や軍事形態は多くの場合、「脅威への対応を含めた国家の戦略的要求」と「社会の価値観や規範等を含む文化的要因」によって定まる。脅威と文化の間には相関性があり、脅威が弱まれば文化の影響は強まり、脅威が強まれば文化的要素を度外視せざるを得ない戦略と軍がつくられる構図となっている。本書は、戦前の日米両軍、および戦後の米軍と自衛隊を文化、脅威および軍事戦略に照らし合わせて考察・比較することで、軍の形成に影響を与えている戦略文化を明らかにする意欲的分析である。
目次
序 章 戦略文化論と軍を形成する条件
第1章 戦前の米軍と戦略文化――「文化」との闘い
第2章 反軍的文化と予備兵力増強施策
第3章 戦略的合理性と反軍的文化により廃案となったUMT構想
第4章 日本軍と戦略文化――「脅威」との戦い
第5章 「外征軍」として発展した日本陸軍
第6章 真逆となった日米の戦略文化と軍隊(自衛隊)
第7章 日本の戦略文化と自衛隊
終 章 異質の文化を絆とする日米同盟
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
119
企業の社風が異なるように、軍隊も各国の歴史と国民性と地政学的事情を反映する。世界最強とされる米軍が「必要悪」として創立され、独立戦争を根源とする米国民の強い反軍的文化から長く冷遇されてきた。一方で外国からの侵略への国民的恐怖下で建軍された旧日本軍は海洋国家であるべき国が大陸国家的軍隊を持ったため不自然に膨張し、対外侵略へ突っ走ってしまった。しかし第二次大戦後の米軍は世界の警察官として君臨し、逆に日本では反軍文化による歪んだ平和主義が浸透した。軍隊も時代や政治の事情が支配する人の集団なのだと考えさせられる。2025/01/05
Miyoshi Hirotaka
18
軍隊には外からの脅威とその国固有の文化面が作用する。わが国の場合、開国以来脅威を基調に建軍され、文化が入り込む余地はなかった。列強各国の軍制が混在したのはこのため。一方、州で構成され、外敵から侵略される可能性が皆無だった米国には文化が作用。このため、平時には州兵、有事には連邦軍形成という仕組みになった。米ソ冷戦後、米国が核の脅威を肩代わりしたため、米国は脅威中心、わが国は文化優勢の組織に変質していった。日米の軍組織の成立は建軍時から真逆。また、先の大戦を機にそれぞれが入れ替わる形で同盟が形成されている。2025/02/02
田中峰和
7
第二次世界大戦で勝者と敗者に別れた米国と日本だが、その歴史において共通する部分もあった。米国は建国時、欧州のような君主制ではなく民主的過ぎたため、軍の強大化を脅威とみなす傾向が強かった。それは戦後日本の左翼系言論が軍事=悪とするのに近い。当然、平和時は軍への依存は軽視され、その規模も縮小される。日米ともに、陸海軍の兵数は驚くほど増えた。ポツダム宣言のとき、日本の陸軍は640万、海軍は186万にもいた。戦後の冷戦は、戦前とうってかわり米国国民は軍の重要性を認め、呑気な日本は軍備を軽視させてきたようだ。2025/03/21
ゼロ投資大学
2
第二次世界大戦以降の日本の自衛隊とアメリカの軍隊の歴史と役割を詳細に分析していく。アメリカでは第二次世界大戦を契機に、軍の意義が確立し、世界の警察として各地で軍事力を行使するようになった。日本は第二次世界大戦の敗戦を機に軍隊は解体されたものの、冷戦下における日本の戦略的価値が増したことにより、自衛隊を組織し、国際秩序の安定への貢献を求められていく。国内では災害対応などで日本国民の支持を得ており、安全保障に留まらない活動が期待される。2024/11/17