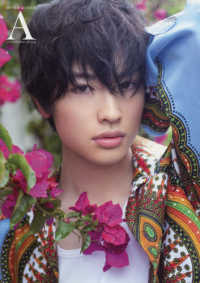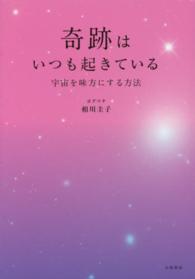内容説明
「毎年来るツバメは同じツバメか?」「小鳥も案外長生きする」「スズメの数が減っている」――本書では100年にわたる「鳥類標識調査」によって明らかになってきた鳥の興味深い生態を紹介しています。鳥に足環などの標識をつけて放す鳥類標識調査からは、渡り鳥がどこから来てどこへ行くのか、鳥が何年生きるのか、身近な鳥の数が減っているといった様々なことがわかります。本書では、日本で唯一の鳥類研究所である「山階鳥類研究所」の研究員が、この鳥類標識調査で明らかになったことを解説しました。
「はじめに」では、絵本作家・鈴木まもるさんの描き下ろしイラストとともに、鳥類標識調査について解説しています。
■内容
はじめに ~私たちは、鳥のことを、どこまで知っているのだろう~
鳥類標識調査100周年に寄せて
1章 渡り鳥が世界をつなぐ
鳥の渡りってなんだろう/鳥の長距離移動チャンピオン/東京と福岡のユリカモメがどこか違う/ツバメの越冬地を求めて/ベニアジサシの越冬地の発見/アジサシ類は天気を呼んで渡る?/先端技術と標識調査/日本にいるハマシギは、どこからやって来るのか/足環で判明したツル類の生態/渡り鳥がつなぐ国際協力の輪
2章 鳥はどれくらい生きる?
毎年来るツバメは同じツバメか/長生きする鳥たち/小鳥も案外長生きする/蕪島に集まる3万羽のウミネコ/アマミヤマシギの奇妙な生活/絶滅の可能性を評価する
3章 鳥たちにせまる危機
激減するカシラダカに何が起きている?/スズメの数が減っている/干潟の鳥シギ・チドリ類に未来はあるか?/温暖化で変わる? 鳥たちの渡り/トキの野外個体群を追う/じつは2種だったアホウドリ/鳥類標識調査が生息地保全に貢献
4章 標識調査でわかる、あんなことこんなこと
雄か雌か? 成鳥か幼鳥か? ~性別や年齢と、標識調査~/多くの情報を秘めた足環つきの収蔵標本/ヤンバルクイナの発見/隠蔽種の存在を明らかにする/「そこにどんな鳥がいるか」を知るためには/人獣共通感染症と渡り鳥
鳥類標識調査について
鳥類標識調査100年の歴史/世界各国の鳥類標識調査/日本の鳥類標識調査/標識調査にかかわる法律の話/バンダーになるには/標識のついた鳥が発見されたとき
コラム
「幸福な王子」が教えてくれること/山岳バンディング/皇居の鳥たち/足環の回収記録が生き別れた親子をつないだ物語/鳥類標識調査への批判に応える/日本鳥類標識協会とは/標識調査と山階鳥類研究所
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サンダーバード@怪しいグルメ探検隊・隊鳥
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
k sato
shiman
ろべると