- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
欧州では、大都市も地方都市も、街の空間を再編し、多様な移動の選択肢を提示することで豊かな生活を実現しつつある。これはEUが提示した「持続可能な都市モビリティ計画(SUMP)」に基づく交通まちづくりの成果といえる。欧州の事例をそのまま日本には適用できなくとも、良いところを学ぶことで活力を取り戻せるはずだ。欧州における最新の取り組みと背後にある考え方、日本の交通政策の歴史的経緯を踏まえつつ、これからの日本に求められる具体的な戦略を提言する。
目次
はじめに/第1章 モビリティが支える豊かな生活/1 宇都宮市──ライトレールがもたらした変化/宇都宮ライトレール開業/小学校が新設されたライトレール沿線/市民参画とライフスタイルの変化/2 富山市──公共交通がライフスタイルを変えた/「お団子と串」のまちづくり/公共交通利用を促すアイディア/公共交通でライフスタイルが変化/3 ひたちなか市──鉄道は町のたからもの/ローカル線の再生/統合学校を鉄道沿線に/町のたからもの/4 小山市──コミュニティバスの挑戦/バスが撤退した街/モビリティマネジメントとサブスクリプション/ライフスタイルの変化/街の変化も少しずつ/第2章 オーストリア・フォアアールベルク州の劇的な変化/1 フォアアールベルク州の概要/2 フォアアールベルクの公共交通/3 手間いらずのきっぷ/4 小さいながら活気のある町/第3章 フォアアールベルクを変えた「ビジョン・ラインタール」/1 市民とステークホルダーの参画/2 ビジョン・ラインタールの掲げる目的と施策/三つの目標と四つの政策分野/メリハリのある土地利用/公共交通を地域発展の背骨に/土地利用と公共交通の政策的統合/街路空間の質の向上/地域アイデンティティのある計画/3 車なしでも実現できる高いアクセシビリティ/社会変革のツールとしての公共交通/未来を見通せる計画と実践/ビジョンづくりの段階から市民を巻き込む/10年で倍増した鉄道利用者/4 大都市並みの公共交通サービス実現のための制度と資金調達/PSOによる契約ベースの運営/列車やバスの本数・運行時間帯は地域戦略/実質三割増予算での実現/5 持続可能なフォアアールベルクへ/第4章 持続可能性とはなにか/1 持続「不可能性」から考える/種の絶滅/乱獲と生態系の破壊/化石燃料/心身の健康/過疎化と一極集中/2 持続不可能なものの特徴/崩れた出入りのバランス/一つの目的だけを追うと…… /明らかになるまでの「時間差」/最適行動の選択の結果としての持続不可能性/3 持続可能な社会づくりのために/「コモンズの悲劇」と持続可能性/「ブルントラント報告書」から「SDGs」へ/社会・経済・環境の持続可能性の両立/第5章 モビリティはなぜ重要なのか/1 社会の基盤としてのモビリティ/「交通」と「モビリティ」のちがい/モビリティは欲求とのギャップを埋める/2 モビリティ実現の手段としての交通機関の発達/徒歩から動力による交通手段への発展/多様化する欲求とモビリティ/3 交通によるエネルギー消費と温室効果ガスの排出/4 交通手段とエネルギー/体の力だけでまかなう徒歩と自転車/自動車の場合/鉄道の多くは電力で動く/交通手段ごとの消費エネルギー量の差/5 地域の社会・経済の持続可能性とモビリティ/地域社会の関わりの基本は徒歩/車優先のまちは歩きにくい/6 持続可能な社会に向けたモビリティの選択肢/第6章 モビリティ計画「SUMP」とは何か/1 SUMPの経緯と概要/交通における持続可能性に向けた取り組みの歴史/SUMPの定義と目標/SUMP策定プロセスの原則と特徴/SUMPサイクル/2 SUMPフェーズ1──準備と分析/市民参加と当事者意識を促進(ステップ1)/都市圏域を確定し、他の計画と関連付ける(ステップ2)/現状分析はデータ収集から(ステップ3)/3 SUMPフェーズ2──戦略の策定/複数シナリオの検討からビジョンと目的を作成(ステップ4~5)/SMARTな目標値を設定──まずは交通手段分担率(ステップ6)/4 SUMPフェーズ3──施策の策定/施策をパッケージで選択(ステップ7)/財源を特定し、優先順位、実施主体、スケジュールを合意(ステップ8)/文書の完成を地域のコミュニティとともに祝う(ステップ9)/5 SUMPフェーズ4──実施とモニタリング/モニタリングによる実施管理で新たな課題を抽出(ステップ10~12)/6 SUMPを巡る新たな動き/世界に広がるSUMP/SUMPの法制化/第7章 欧州から何を学ぶことができるのか/1 交通まちづくりにかかる日本の制度/2000年以降整備された日本の制度/制度運用の現実/2 バックキャスティング・アプローチ/需要追随型からバックキャスティング・アプローチへ/日本の問題/3 EBPM──エビデンスに基づいた政策づくり/バックキャスティング・アプローチとEBPM/目的にそった手段かを見極めるEBPM/エビデンスの批判的な検討と蓄積が必要/4 データ整備/遅れる日本の統計整備/交通手段分担率/アクセシビリティ指標/公共交通のサービス水準指標/5 統合的な施策策定/縦割りからの脱却/パッケージとしての施策/ダウンズ・トムソンのパラドックス/ジェボンズのパラドックスとリバウンド効果/6 事業評価と財源確保/費用対効果/財源確保/交通税/第8章 日本の課題と戦略──豊かな未来に向けて/1 持続可能性を交通まちづくりの目的に/評価軸を見直す/バックキャスティングで評価軸は変わる/2 公と民の役割分担の見直し/「市場の失敗」の是正/PSO(公共サービス義務)の導入/「民から公へ」のイギリスも手本に/3 戦略の策定に向けた知恵の結集/STO/市民参画によるビジョンと戦略の策定/道路の計画も交通の戦略に組み込む/産官学の連携、人材の交流/4 夢とビジョンをもってまちづくりを/あとがき/参考文献
-

- 電子書籍
- 優しい義母のウラの顔 18 LScom…
-

- 電子書籍
- 高速有鉛デラックス2018年4月号
-

- 電子書籍
- ぷにぷにぷにおちゃん ~赤ちゃん観察日…
-
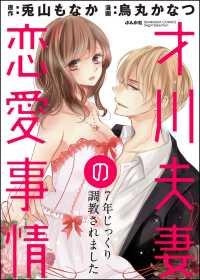
- 電子書籍
- 才川夫妻の恋愛事情 7年じっくり調教さ…
-
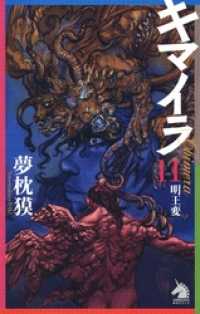
- 電子書籍
- キマイラ11 明王変 ソノラマノベルス



