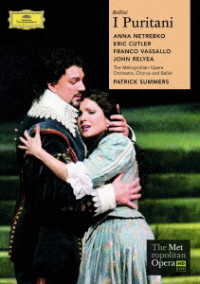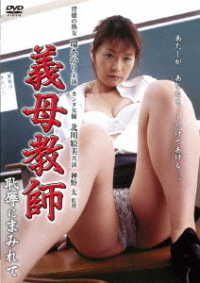内容説明
宮本常一の膨大な仕事のなかでも自らの生い立ちにつながる島嶼振興にかかわる仕事は、終戦から最晩年までを貫くものであった。島の青年を愛情を込めて鼓舞する「後継者の育成と推進員の社会的使命」、自らの離島振興の仕事を振り返った「本土における離島振興について」、最晩年に郷里、周防大島で島民に語った「よりよい郷土をつくりために」、さらに県内のことごとくを歩いた経験をもとに、広島県中山間部・三次市で、地域文化の自主性を説いた「中国地方の文化と生活」など、10編の講演を収める。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroki Nishizumi
2
この巻の講演は、農業には適正経営面積があるとか港湾整備や船の大型化するべし、といったある意味真っ当な展開であった。常一自身も離島振興法に関わるようになり、目に見える成果を求められていた時期だと思う。ただその分何かしら物足りなく感じるところが多かったように感じる。元々貧しかった津山で高専誘致をきっかけに郷土出身の学者リストをつくりそれが次々と大学建設に結びついたくだりは参考になった。2015/08/04
R
1
宮本常一の前半生は民俗学の調査にささげられ、後半生は民俗学の知見を活かした地域振興にささげられた。現状の日本を見たらどんなことを言うだろうか。2022/07/20
-

- 電子書籍
- MONOQLO 2022年 2月号