内容説明
日本古来の布・衣と紙を植物の茎皮繊維の利用という共通性からとらえ、その生活文化を日本の柔社会の特徴として浮き彫りにした「生活文化研究講義」、晩年に集中して話された「日本文化の形成」につながる「煮ることと蒸すこと」、日本人が何をたべてきたかを語る「日本人の主食」など、6編の講演録を収める。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
39
民俗学者の講演集。布の変遷、紙の変遷から民俗学の未来まで、様々な話題が収録されている。前半は大学の講義が収録されており、藁や織物の変遷、紙の産地が日本において何故変化していったか、欧州と日本の都市等、どこを読んでもわかりやすくまた興味を惹かない部分は無かった。後半も東西日本の食文化の違いや、主食の事等いずれも夢中で読む。話者が自分の旅の事を語っている部分もあるけど、そこは何となく食べ歩きっぽい感じで面白かった。そこで食べたものが食卓も均一化された現在、特別な食べ物となっているだろうことが何となく寂しい。2014/02/02
Hiroki Nishizumi
5
面白いね興味深いね。畳はたたむもの、藁が築きあげた日本文化。紙(和紙)と暮らしについて。庭に柿の木を植えていたのは渋をとるため。日本食文化の浅い歴史について。などなど・・・2015/06/22
なにょう
3
文化の基本的なものは最初に敷かれたレールの上をずっと今日まで来ています。 …筆者の語る日本と私の知っている日本は別物のように思えることがあるけれどもきっと繋がっているんだろうな。2014/07/14
R
2
自身が過去に歩き回った旅の経験のと文献的な知見が融合し,民衆文化を柱とした独自の日本感が表現される。決してサムライの国ではない。白米ですら日本食のスタンダードではない。今の自分たちが信じている日本,信じたい日本とは違う姿を語り掛けてくれる。2022/06/18
Nunokawa Takaki
1
民俗学の世界ではその存在感を放っている宮本常一氏。この本には、彼が語った体験、情報がぎっしり詰まっている。なぜ日本人は戦争をしてこなかったのかをベースに、茎皮繊維のあれこれ、日本の住宅、食文化など多岐にわたり言及している。ただ机上で勉強して得た知識だけでなく、実体験がちりばめられているところに説得力を感じた。2016/06/09
-
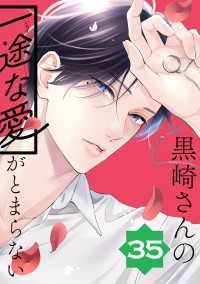
- 電子書籍
- 黒崎さんの一途な愛がとまらない【単話版…
-
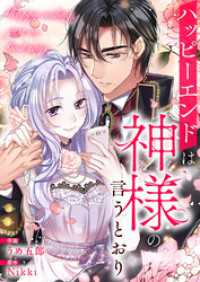
- 電子書籍
- ハッピーエンドは神様の言うとおり【タテ…
-
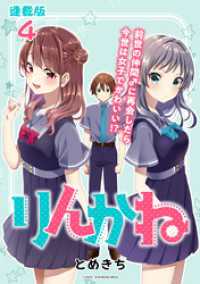
- 電子書籍
- りんかね 連載版:4 ブシロードコミッ…
-

- 電子書籍
- 胸キュンスカッとコミック版~恋も部活も…
-
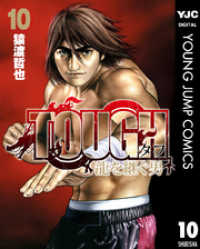
- 電子書籍
- TOUGH 龍を継ぐ男 10 ヤングジ…




