- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
映像制作を支えるスゴ腕裏方の技術と情熱。
近年に大ヒットした映画やテレビドラマには、実は重要な役割を果たしているディテールがある。裏方として映像制作を支えるスタッフたちは、いかにしてそれを創り上げ、ヒットに導いたのか。VFX、音響、殺陣、特殊メイクなどを担う“職人”12人の技術と情熱を知れば、映像鑑賞がもっと面白くなる!
本書に登場する「職人」は以下の12人です。(五十音順)
特殊メイクアップアーティスト 江川悦子
(映画『おくりびと』、大河ドラマ『麒麟がくる』『青天を衝け』)
鉄道具制作 大澤克俊
(映画『ゴジラ -1.0』『永遠の0』)
音楽家 梶浦由記
(劇場版『「鬼滅の刃」無限列車編』)
音響効果 柴崎憲治
(映画『この世界の片隅に』)
VFXディレクター 白石哲也
(映画『るろうに剣心』シリーズ、ドラマ『全裸監督2』)
役馬調教・馬術指導 田中光法
(大河ドラマ『鎌倉殿の13人』)
人物デザイナー 柘植伊佐夫
(映画『翔んで埼玉』シリーズ、大河ドラマ『龍馬伝』『どうする家康』)
殺陣指導 中川邦史朗
(大河ドラマ『真田丸』)
ポスターデザイナー 中平一史
(映画『アウトレイジ』シリーズ)
キャスティング・ディレクター 奈良橋陽子
(映画『ラスト サムライ』『終戦のエンペラー』)
デジタル・リマスター 根岸誠
(「東映」旧作映画)
池袋シネマ・ロサ劇場支配人 矢川亮
(映画『カメラを止めるな!』)
(底本 2024年10月発売作品)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
keroppi
67
映画の裏方である職人たちへのインタビュー集。しかも、昔ながらの職人というより、今の時代の職人たちだ。デジタルに関連するものも多い。「人物デザイナー」とか「鉄道具」というのは初めて知った。「鉄道具」で登場するのは「ゴジラ-1.0」で「震電」を作った人だ。最新技術を扱う方々も、リアルに鉄で作ったものは認めている。デジタルで作るより、質感が違うし、なんといっても役者の演技が違うらしい。今の映画界も、こういう職人たちによって支えられているんだなぁ。2024/12/18
nonpono
66
中高一貫校の女子校で、演劇部に入部。先輩は怖いわ、毎日、部活はあるし、一年で辞めようとしていたら六年続きました。同期との出会いもそうですが、「みんなで何か一つのものを作る」という麻薬を味わいました。だから、本書は興味深かった。日本映画を支えるメイクさんからキャスティングプロデューサー、VFX、殺陣、乗馬、美術などの一流の方へ春日太一が話を聞きに行く。みんな、それぞれのアンテナがあり、こだわりがある。やはり、仕事も縁もありますね。真摯に向き合っていけば見ている人は必ずいるんだなと。好きこそものの上手なれと。2024/12/22
ヒデキ
45
一気読みしてしまいました。 春日さんの作品なんで、てっきり70年代くらいの職人さんの話かな?と思っていたら、 前書きで現代の職人さんの話と断り書きがあって 「あ~」と思いましたが、 とっても興味深く読めました。 聞いたことのない肩書の方もあり「どんなお仕事?」と思って読み出すと作業が、細分化されて深くなっていることを知ることになりました。 今後も楽しみなシリーズです 2024/10/04
道楽モン
38
邦画、特に時代劇を研究対象としている春日太一にしては珍しいテーマで、近年ヒットした邦画の作り手であるスタッフに注目した、各部署担当の職人さんへのインタビュー集。大手5社の時代から俯瞰すると、映画の撮影技術は長足の進歩を遂げている。取り上げられた作品にも、観たこともないアングルやアクション、美術などが、デジタル技術を駆使した新しい表現手段を獲得しているものが多い。ところが、本書によると、それらの技術を支えているのは、職人として腕を磨いたアナログな方法を土台としていることが判る。綿々と続く映画魂は不滅なのだ。2024/10/25
ぐうぐう
31
意外な一冊だ。旧作の邦画について論じてきた春日太一が、現在の日本映画を対象にする。しかも、裏方である職人にスポットを当てるのだ。さらに裏方といっても、人物デザイナーやデジタルリマスター、撮影美術制作でも鉄道具を取り上げるなど、なんとも渋いチョイスがたまらない。また、アニメーションならではの音響効果の苦労を語る柴崎憲治、CGに関して「ツールが変わっただけ」でそこには昔ながらの職人魂があるという白石哲也など、なるほどと思わせられる証言を春日は引き出している。(つづく)2024/10/10
-

- 電子書籍
- 幸福論 白水Uブックス/思想の地平線
-
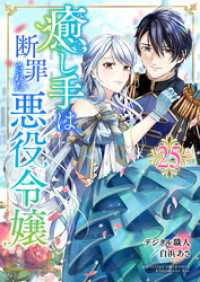
- 電子書籍
- 癒し手は断罪された悪役令嬢 25話 e…
-
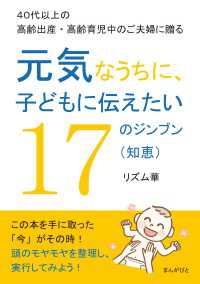
- 電子書籍
- 40代以上の高齢出産・高齢育児中のご夫…
-

- 電子書籍
- 爆宴(5)
-

- 電子書籍
- Dr.クロワッサン 体に効く 野菜の大…




