- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
天明期、江戸で狂歌が大流行した。狂歌とは、五七五七七の形式に載せて滑稽な歌を詠む文芸である。ブームの仕掛け人・大田南畝の昂揚感のある狂歌は多くの人を惹きつけ、誰もが気軽に参加できるその狂歌会は流行の発信源となった。楽しい江戸のまちの太鼓持ち「狂歌師」という役どころは、いかにして人びとを魅了したのか。平賀源内や山東京伝にも一目置かれ、蔦屋重三郎の良き助言者であった大田南畝の人物像がわかる決定版。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
39
大田南畝は、書物を読み書写することを愛し、自己を措いて、書物に向きあった(7頁)。人一倍勉強家だった(19頁)。寝惚先生は我が身の貧乏もネタにする。「上下敝(かみしもちぎ)れ果てて大小賤(きたな)し 憶(おも)ひ出す算用昨夜の悲しみ 昨夜の算用立てずといえども 武士(さむらい) 食はねど高楊枝 今朝の屠蘇 露ほども未だ嘗めず」(195頁)。著者の解説は、身につけた裃(かみしも)も破れ、大小の刀も薄汚い。昨晩の掛け金の支払い苦労を想い、成らなくとも武士は鷹揚に構える。2025/08/14
アオイトリ
28
大河ドラマ)ありがた山の寒カラス!と地口が面白い蔦重の時代。狂歌の大流行についての社会学的考察です。間髪おかず次々と技巧を重ねておかしみを生み出す高揚感が好き。よきことを思ひ出せばあかつきに寝られぬ老もめでたかりけり/びんぼうの神無月こそめでたけれあらし木がらしふくふくとして/早蕨の握りこぶしを振りあげて山の横つらはる風ぞふく(マイベスト)。それぞれが「役」を担うことで社会が成り立つと考えていた江戸期の日本人と自分らしさを肯定する私たちは違う。わかったような気になるなよ、という解説も興味深かったです。2025/05/18
gorgeanalogue
12
全体にまあまあ面白く読めたが、おそらく著者も十分に自覚している通り、「めでたさ」をあおる狂歌師という「役」を強調しまた著者自身がその役回りを演じようとするあまり、そのはしゃぎぶりがやや鼻につく。また、「あとがき」にある「近代的個人」と近世的「役」の整理は図式的で説得力はない。2024/12/25
広瀬研究会
5
洒落やパロディといった言葉遊びが好きだから、大田南畝というか大田蜀山人というか四方赤良には興味津々だったけど、こうしてまとまった読み物に触れるのは初めて。皮肉や風刺にはのめり込まず、貧乏もトラブルもめでたいめでたいと言って笑い飛ばす芸風が好きだなあ。周りに登場する人たちも酒上熟寝(さけのうえのじゅくね)やら宿屋飯盛(やどやのめしもり)やら磯野若女(いそのわかめ)やら、今も昔もやってることあんまり変わらんのが可笑しいですね。2025/05/31
tayata
4
飢饉や災害といった激動の時代に狂歌をみんなで楽しんでいる時代の空気や当時の日本人の教養の高さを感じられた。2025/01/24
-

- 電子書籍
- 異世界マッサージ 残念エルフ魔法医に愛…
-
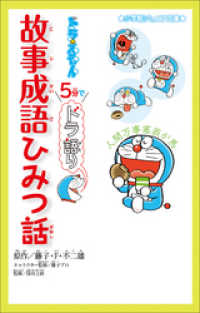
- 電子書籍
- 小学館ジュニア文庫 ドラえもん 5分で…
-

- 電子書籍
- 槍の勇者のやり直し 4 MFC
-

- 電子書籍
- ウクレレ・マガジン・アーカイブ・シリー…
-
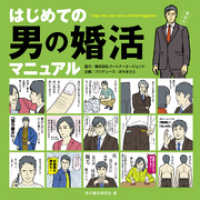
- 電子書籍
- はじめての男の婚活マニュアル




