内容説明
普段飲んでいるその薬、「なぜ効くのか」知っていますか?薬が効くしくみを、「化学」と「生物」の基礎的な内容をおさらいしつつ、徹底的にわかりやすく紹介。むずかしい計算などもなく、構造式を眺めるだけで、薬のメカニズムや製薬の裏側がわかるように説明していきます。製薬の裏側や、医学・薬学の歴史も学べます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
☆よいこ
79
内容確認読み。薬のしくみについて書かれた本は調べ学習にもよく選ばれるテーマなので▽[1.薬が効くまでの道のり]タンパク質[2.「発熱」と「痛い」はなぜ起こるのか]やさしさ=合成ヒドロタルサイト酸を中和[3.アレルギーの鍵穴を埋める][4.体を襲う菌・ウイルスと戦う][5.生活習慣病を化学する][6.じつは奥深い胃腸薬の世界][7.より安全な精神科の薬はどうやって生まれたか][8.倒すべきは自分由来の細胞]DNA[9.自分を守るはずの免疫が、病気の原因に]▽参考文献あり。割と使えそう。2024.9刊2025/01/08
たまきら
35
なんとな~くでしか理解できていなかった薬の仕組み。正直、「わからないけれど効果がある」ものも多い気がしますが、こういう説明が自分が使う薬全てでしてもらえたら、すごく学べることが多いだろうなあ。将来的に薬はコンビニでも買えるようになるでしょうし、薬剤師とおいう資格も色々苦難があるのかもしれません。でも、きっと差別化を図ればきっと、良い道はあるはず…。この本買っちゃおうかなあ…。 2025/04/05
チャー
22
薬が効く仕組みを具体的に解説した本。何かしらの病を患ったときには市販の薬に頼る機会も多いが、症状別にそれらの薬が人体に作用するプロセスを具体的に解説しておりわかりやすい。人の症状が起きる原理も踏まえて説明されており大変参考になった。解熱鎮痛剤にも種類があり、はたらきかける対象は成分によって異なっているようだ。対して、病の発祥減となるウイルスや菌も変異や耐性を身につけ薬が効かなくなってくるものもあるとのこと。薬の役割や機能を知ることで、使いどころと適正な容量を考えておくことは、日頃の備えとして大切と感じた。2024/12/17
tetsubun1000mg
17
「なぜ薬が効くのか?」タイトル通りの解説書。 体内のたんぱく質と酵素で体内の化学反応を起こさせる=薬がたんぱく質に結合するという。 図説される化学式はすっ飛ばして文章と説明図のみを読み進める。 発熱と痛み、アレルギー症状に処方される薬とその役割、細菌とウイルスの違いと抗ウイルス薬の仕組みなどは大まかには理解できた。 生活習慣病、がん細胞の章までは何とかついていくが精神科の薬、自己免疫疾患の章は理解が追い付かなかったなあ。 しかし、今まで読んだ事のない分野の本だったので興味深かった。2025/02/27
kanki
17
タンパク質と結合。まさに糖尿にするSGLT阻害薬。インスリンは内服無理。アセトアミノフェンの機序はわかっていない。絵でわかりやすい。 2025/01/22
-
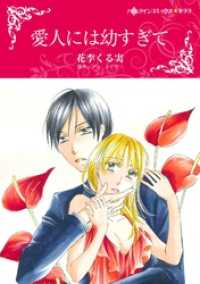
- 電子書籍
- 愛人には幼すぎて【分冊】 10巻 ハー…


![これだけでOK!仕事に使える ワード・エクセル・パワーポイント 〈2024年〉 [テキスト] (増補・最新改訂版)](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48663/4866366737.jpg)





