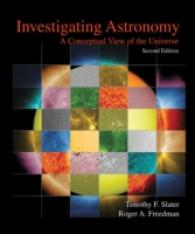- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
コミュニケーション論の不朽の名著! 今こそ求められる「対話」の真髄を語る。
人はなぜ対立するのか。なぜ関係が行き詰まるのか――。
不毛な争いを避け、皆が望む未来をつくる「対話(ダイアローグ)」という方法。
対話(ダイアローグ)とは:
・情報やアイデアではなく「意味」を共有する。
・明確な「目的」を定めなくてもいい。
・人を「説得」することは必要ない。
・あらゆる「想定」を保留することが重要。
「対話の目的は、物事の分析ではなく、議論に勝つことでも意見を交換することでもない。いわば、あなたの意見を目の前に掲げて、それを見ることなのである」
「『愛があればすべてうまくいく』と言う人がいる。だが残念ながら、すべてを救う愛は存在しない。だから、もっと良い方法を考えなければならないんだ」
偉大な物理学者にして思想家ボームが長年の思索の末にたどりついた「対話(ダイアローグ)」という方法。「目的を持たずに話す」「一切の前提を排除する」など実践的なガイドを織り交ぜながら、チームや組織、家庭や国家など、あらゆる共同体を協調に導く、奥深いコミュニケーションの技法を解き明かす。
ベストセラー『学習する組織』著者ピーター・センゲ(MIT上級講師)推薦!
(本書の構成)
1.コミュニケーションとは何か
2.対話とは何か
3.集団思考の性質
4.問題とパラドックス
5.見るものと見られるもの
6.保留、肉体、自己受容感覚
7.参加型思考と無限
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
18
論破だとかディベートでの勝利だとかの先には群れとしての幸福ってありえないだろうなとは常々感じていたけれど、そうしたものとは全く異なる対話の意義と重要性について語られていてとても良かった。完全な相互理解や共通認識を創り上げることは至難の業であり、人類が滅び去るまで叡智を積み重ねたとしてもそこには至れないのかもしれないけれど、近づこうとする努力は放棄してはいけないよな。主義主張や思想信条を互いに分かち合い、理解出来ない存在を決して切り捨てず、共生し共存していく道を探るために言語と対話は存在している。2022/04/24
コジターレ
11
ダイアローグとは何か。表層は理解できてきたと思う。しかし、ビジネスパーソンがダイアローグを受け入れるか、本当に人々は共通理解ができるのかという点については、僕自身の中で整理できていない。ダイアローグに懐疑的なのではなく、むしろとても好きな考え方であり手法なのだが、僕自身が現代に生きる人々が変わる可能性に懐疑的なのかもしれないと思った。2018/02/03
kanaoka 58
8
良書。人間、思考、意見、自己についての考察が明瞭で分かり易い。思考とは生物の反応としてなされる物質的なプロセスである。思考は世界を分離し、その分離されたものが意見である。そして、そこに自己という事象が作り出される。テーマである「対話」を介して集団的思考に至る。それは人類共通の暗黙の領域から生れ、人類や自然との関係性の認識を深める。大脳新皮質による論理的な個人的思考は、断片的であり、世界に対する非干渉的な想定、幻想を強める。生きるための手段・道具であるが、それが目的化すれば、その矛盾は混乱をもたらす。2016/11/13
おサゲっち
7
「対話が大事」とか、「交渉テーブルに相手を座らせ対話する」とか言うけれども、そもそも対話って何だ。多数の人間が語りあい、思考が流れていく状態。輪になって座り、決定したり強制したりしない関係。プロセスそのものが、自己省察を生み、対立から共生へと変容する。不毛な争いが起きずに済む、、、と言うことで、会議で実践してみた。コミュニケーションとして面白く、実践を繰り返しているところだ。2022/02/12
roughfractus02
6
電場では正負の電荷の反発や誘引が場を作る。量子力学者として出発した著者はこの考えを拡張し、場を作ることが生きて存在することであるとした。ピーター・ゼンゲの序文を付した本書は組織論として読まれがちだが、動的な生態こそ世界である、とするホーリズム的主張でもある。意思決定や問題解決より保留を、一致より類似を重視する対話は「何かを共通のものにすること」(コミュニケーション)への努力であると著者はいう。「意味の流れ」としての対話自身が場となるという観点からは、与えられた空間で個を戦わせる議論はデカルト的すぎるのだ。2022/02/24
-

- 電子書籍
- 臨床哲学への歩み