内容説明
1776年に独立を宣言した13植民地がイギリスとの戦争に勝利し、憲法を創り、合衆国に生まれ変わったアメリカ革命。人民主権、三権分立、二大政党のモデルは、民主政治の基礎となった。なぜ弱小国は革命を遂げ、覇権国家になったのか。植民地時代から独立戦争、建国者たちが死闘を演じた憲法制定、党派の始まり、南北戦争へ。大西洋をこえたスケールから、先住民・黒人奴隷の視点もふまえ、70年の歴史を清新に描きだす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
141
世界史の教科書では「植民地アメリカで独立を求める戦争が起きた」とのみ記述されるが、対英戦争勝利から今日に至る政治体制の基礎が築かれるプロセスを革命として捉える。独自性の強い13植民地が独立という一点で共闘し勝利したが、新国家建設の大方針を定める連邦憲法制定会議で自らの有利を図るため激烈な論戦と政治工作を重ねる有様は政治劇を観ているようだ。フランスやロシア革命では一部勢力が全権力を握るため粛清を重ねたが、アメリカでは議論と妥協の末に民主政体が成立した。この原点を知らねば、あの国を正確には理解できないだろう。2024/10/13
skunk_c
100
これは面白い!特に前半のイギリスと13植民地の間の2項対立的な教科書的通説に対し、多くの実例を挙げてそんな単純なものではないことを述べているのがいい。アメリカ史は実際のところかなりの成功の歴史として潤色されている印象があったが、そうした面を遠慮なく引き剥がしているようだ。また独立から憲法制定への過程も詳しく、さらにトランプがその再来と言われたジャクソンの登場まで、奴隷制や先住民への迫害という負の「非民主的」な面をきちんと示しながら論じていく。関税を巡る南北の対立も独立当初からのものとして書かれている。2024/09/05
kk
43
図書館本。独立前夜から米墨戦争の頃にかけての、合衆国の誕生・発展の歩み。立憲過程やその意義を縦糸としつつ、連邦権力の伸長、国際関係における立ち位置の変化、党派の形成を含む国内政治の成熟、そして西部開拓等に代表される「帝国化」のプロセスなどにフォーカス。憲法制定会議における議論や各邦議会における批准過程などが丁寧かつ要領良く紹介されており、勉強になること頻り。他方、アメリカ革命全体における位置付けという点では些かオーバーウェイト? 書き下ろしの新書と言うよりも、寧ろ選書から注を省いたもののような読み応え。2024/09/06
特盛
37
評価3.4/5。大統領選挙の時に図書館で予約。選挙の熱狂が落ち着きだしたのを尻目に読む。支配を強める英国から自由を勝ち取る独立、という従来の構図の裏には内戦的側面など様々な思惑が。成文憲法は大きな成果だが成立時には立法に関わった州代表は全員がなんかしらの不満を持っていた。だが一旦形になるとフェデラリストたちは各自の州で批准の為に団結する。その後実際に運用しながら修正し、ずっと憲法を受け継いできた歴史が今に至る。大陸大国との確執や、米国自体の帝国化の暗い側面など、最新研究を反映した様々な”実は”に触れられた2024/12/12
サアベドラ
36
アメリカ独立革命の過程を連邦憲法制定を軸に描いた新書。2024年刊。一般のアメリカ人が思い描く (そして日本人が高校世界史などを通じてぼんやりと知っている) ピューリタンや建国の父達に彩られた神話的アメリカ建国の物語は、現代史学では独立元の英国、ライバルの西欧列強、当時決して無視できない存在だった先住民諸邦、そして邦内の黒人や女性、非英国人らの視点などにより相対化させられ、仏革命と同様に近代の出発点として無批判に受け入れることができないものとなっている。アメリカとは何なのか、考える切っ掛けを与えてくれる本2025/01/31
-

- 電子書籍
- 災厄令嬢の不条理な事情 婚約者に私以外…
-
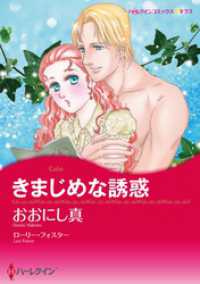
- 電子書籍
- きまじめな誘惑【分冊】 7巻 ハーレク…
-
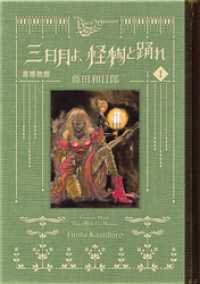
- 電子書籍
- 黒博物館 三日月よ、怪物と踊れ(1)
-
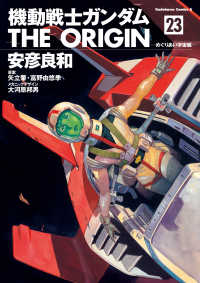
- 電子書籍
- 機動戦士ガンダム THE ORIGIN…
-
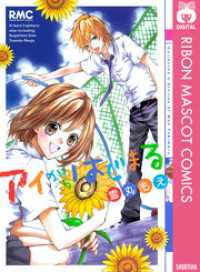
- 電子書籍
- アイからはじまる りぼんマスコットコミ…




