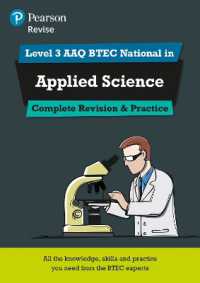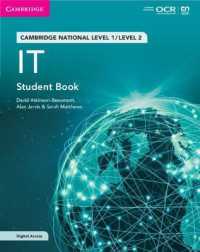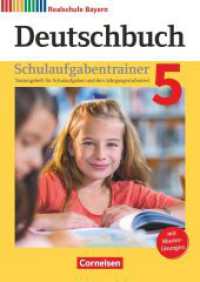- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
SNS時代の今だからこそ、メルマガがマーケティングの武器になる!
本書では、メールマガジンの第一人者が、誰でもメールマーケティングで成果を挙げられる「定石」をご紹介します。
SNSが普及した今でも、メールマーケティングはコストパフォーマンスに優れたマーケティング手段の1つです。
一方で、漫然と配信しているだけでは、手間がかかるわりに成果が出しにくいのも事実です。
メールマーケティングの成果は、配信する「リストの質」と「タイミング」、購買につながる「コンテンツとレイアウトの型」の3要素が鍵となります。
3要素を最適化していけば、誰でも顧客を動かし、集客・購買といったコンバージョンにつなげることができます。本書ではそのプロセスを、順を追って解説します。
定石に従った振り返りと改善のサイクルを回せば、文章力もデザインスキルも不要で、手間なく成果を生み出せます。
【こんな方におすすめ】
●メールマガジンの運用を担当し、ネタやコンテンツの準備に悩んでいる方
●自社のメールマガジンの成果が不明確で、次の打ち手に悩んでいる方
●SNSマーケティングなど他の手法に取り組んでいるが、いまいち結果につながらない方
【本書のポイント】
●メール配信ツールの事業責任者を務めた第一人者が、培った知見を書籍化
●成果を生み出すためのプロセスを、ステップバイステップで解説し、次の打ち手がわかる
●「クリック率」や「開封率」などの指標の見方、「特定電子メール法」や「DKIM」など覚えておきたい知識も紹介
●特典の「指標振り返りシート」で、配信の成果を容易に分析できる
●BtoB/BtoCの両方に対応
【目次】
・序章 なぜ、メールマーケティングか
・第1章 メールマーケティングを始める前に
・第2章 質の高いリストをつくるプロセス
・第3章 手間を省いて成果を生み出すコンテンツの型
・第4章 読まれるための配信タイミング
・第5章 振り返りとテクニックで成果を最大化する
・第6章 迷惑メール扱いを防ぐ対策と知っておくべきメールの法律
※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
SABA
kan0427
sho-kk
Go Extreme
ほんべる
-

- 洋書
- Kaleidoscope
-
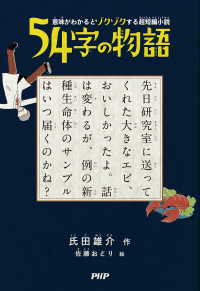
- 電子書籍
- 意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 …