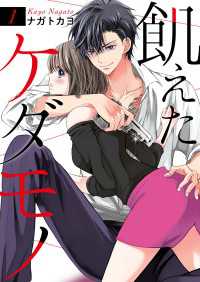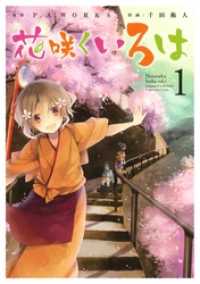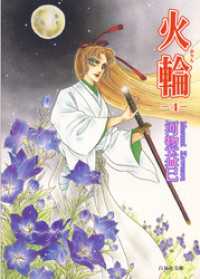内容説明
江戸時代後期、下総のとある藩。郷士の望月鞘音は内職で、傷の治療に使う「サヤネ紙」という製品を作っていた。ある時、幼馴染の紙問屋・我孫子壮介から、その改良を依頼される。町の女医者・佐倉虎峰がサヤネ紙を買っていくのだが、使い勝手が悪いと言っているらしい。しかしそれは「月役(月経)」の処置に使うためであった。穢らわしい用途にサヤネ紙を使われ、武士の名を貶められたと激怒する鞘音だったが、育てている姪が初潮を迎えたことを機に、女性が置かれている苦境とサヤネ紙の有用性を知り、改良を決意する。「女のシモで口に糊する」と馬鹿にされながらも、世の女性を「穢れ」の呪いから解放するために試行錯誤を続ける鞘音。ついに完成した製品を「月花美人」と名付け、販売に乗り出そうというとき、江戸へ参勤していた領主・高山重久が帰国する――。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
いつでも母さん
141
何が穢れだ!女だけが何故穢れだ!人は女から産まれてるんだぜ!本作はそれが根底にあり、それが全てを物語ってると言って過言ではない。商品名『月花美人』を売り出すまでの艱難辛苦・・それはあの時代の革命(よなおし)壮介、虎峰、鞘音それぞれの闘いを熱く読んだ。2025/01/17
となりのトウシロウ
84
江戸時代、血は穢れ、女人は穢れ、月経禁忌とされた時代に、武士と町人と女医が生理用品を開発し悪しき慣習に立ち向かう。剣鬼と呼ばれる武士・鞘音の姪であり養女・若葉の日記から綴られる物語。月経だけではなく、武士とは、女とは、こうあらねばならない(こうあってはならない)というとにかく生きづらい時代をそこから脱して己の信じる道を突き進む力強さが登場人物達には感じられます。生理用品一つでここまで事態がこじれるのかと驚きますが、それがこの時代だったのでしょう。ちょっとしたコメディが随所にある読みやすい時代小説です。2025/05/06
タイ子
81
江戸時代に生理用商品を開発する人がいたなんて。商売は何事も需要と供給で成り立っているわけですが、必需品とみなされなければ売れないし、買わない。これを手掛けた3人の幼馴染の男女。紙問屋の若き主人、義理の娘を育てる武士、3代目女医。3人のうち、誰が欠けても成し得なかった商品開発。ましてや、穢れてるだの、不浄小屋だの、血盆経を唱える坊主まで。参勤交代の殿様が帰藩してからまたひと騒動。無事でいてくれと祈るばかりの後半戦の面白さ。価値観とか正当性とか理屈抜きで全てが目新しく、全てに敬意を表したい作品。2025/04/07
のぶ
81
江戸末期のプロジェクトXですね。主人公は一流の剣客という設定ながら、内容は生理用品作り、というストーリーが以外で面白かった。主人公は剣術修業に明け暮れていた望月鞘音。自ら漉いた紙が女医師の佐倉虎峰によって、女のための月役紙として使われていると知り、思わず激怒するところが始まり。しかし、姪の若葉が初潮を迎え、その大変さを知ることになったことから、考え方を改める。女性たちを月一回の苦しみから少しでも救おうと挑んだ、鞘音・壮介・虎峰の奮闘ストーリーで、ひたむきに目的をもって突き進んでいくところに熱くなった。2024/09/28
ゆみねこ
75
菜澄班郷士・望月鞘音は傷の治療に使う〈サヤネ紙〉を作り、亡き兄の遺児・若葉との暮らしの糧としていたが、幼なじみの紙問屋・我孫子屋壮介と女医者・佐倉虎峰は「月役」の処置に使うため〈サヤネ紙〉の改良を持ちかける。女性の生理を穢れとし忌み嫌う時代に、武士としての誇りや立場を乗り越えて〈月下美人〉を開発し売り出そうとした彼らの前に立ちはだかるものは?着眼点が面白く、楽しい読書が出来た。女を穢れたものと言うなら、その女から生まれた男は何なのか?いつも疑問に思う私です。2025/02/11