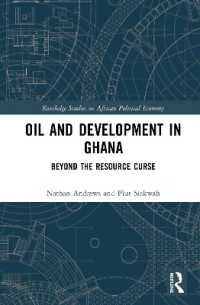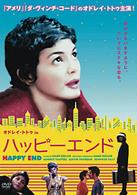内容説明
100年前の「台所改善運動」、戦後のシステムキッチンを経て日本の台所はどこへ向かうのか? 台所と住まいの100年の変遷を辿る
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
137
戦後日本では専業主婦が家事一切を担うのが当然とされてきたが、住まいは生活空間の快適さが優先された。食文化の研究でメニューや食材は主題となるが、料理を作る台所は付け足し扱いだった。公団住宅でシステムキッチンが広まると快適で近代的なキッチンが求められたが、持ち家政策が優先される日本では、諸外国のような家賃補助制度がないので家を買えぬ人は暮らしの質を考えない賃貸住宅に入るしかない。いわば住宅政策の負の部分が、キッチンに押しつけられ続けた歴史が見えてくる。この部分から改めねば、日本人は減り続けるばかりではないか。2024/10/21
とよぽん
49
1920年ごろ、大正時代の中期から日本の台所が変わり始める。それは、第1次世界大戦後の世界の住宅事情とも重なる部分がある。しかし、日本では台所を住居の中心と考える文化はなく、毎日の食事作りを担う女性たちには台所が不便と不自由と重い負担になる。以前、阿古真理さんの「家事は大変って気づきましたか?」を読んだときも、この方はジェンダーや女性の生き方に対する確固たる視点をもっていると感じた。本書でも、338ページの「庶民に居住権はあるのか?」という見出しの文章に、日本の住宅政策の根本的な欠陥を指摘している。2025/01/29
hitotak
12
賃貸、建売住宅の備付キッチンは狭く、動線も悪い。賃貸アパートの台所の使い勝手の悪さ、例えばコンロの後ろに冷蔵庫を置く使いづらさが当たり前の事とされているのは何故なのか、という事が詳しく論じられている。戦後の住設メーカーや不動産会社が台所を重視せず、日常的に料理をしない男性たちが(妻の意見を聞こうとも思わず)設計したせいではないか、というのは納得。今まで見てきた台所の記事は、収納の工夫や見栄え、清掃、あるいは台所を舞台にした人生模様であり、台所自体の不備を問うものはなかったのでは?その意味で新鮮だった。2024/11/24
とりもり
5
労作だがやや散漫な印象。確かに、売る技術だけが突出した不動産デベロッパーに本当の生活目線はないので、どうしても見た目が優先されてキッチンの使い勝手は後回しにされがち。ワンルームに代表される狭小賃貸住宅では、何と言っても居住スペースを少しでも広く見せること、そして何より料理をしないことから最低限のキッチンスペースしか確保されない。そこに大きな不満が出ないのは、著者が思うよりもキッチンへの要望が少ないこともあるのでは。確かに、コンロの後ろに冷蔵庫というレイアウトはやめてほしいけど。★★☆☆☆2024/10/06
紀梨香
5
そんなに都会に住んでいたわけではないのに、歴代の賃貸住宅の台所は本書にあるとおり使いにくものばかり。今から戻れと言われたらとんでもないストレスだと思う。先日家族が住むことになった単身者向けの部屋のキッチンを使ってみて痛感しました。日常的に台所を使っていない設計者が作ったキッチンが多いから。マンションの設計上キッチンがいつも後回しだから。日本の家庭のキッチンにはモノが多すぎるから。色々理由はあるけれど戦後の政府が庶民の住環境に無関心で自己責任となっていたのが一番大きかったのではないだろうか。2024/08/23
-

- 和書
- 基本簿記演習