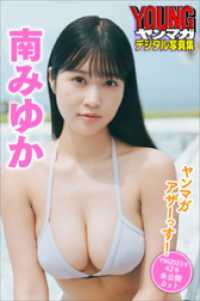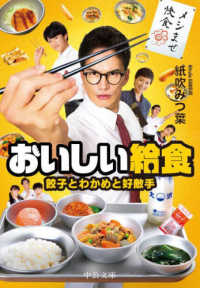内容説明
開戦の姿を克明に描いた傑作ドキュメント
1941年12月8日、日本軍は真珠湾を奇襲攻撃した。なぜ「必敗の戦争」を始めたのか。7カ月に及ぶ熾烈な外交交渉の内幕、その果てに訪れた開戦の日の24時間の詳細な推移とは。膨大な公刊資料、証言、日記などを元に、東京、ワシントン、ホノルル、マレー半島と舞台を移しながら、克明に記録した傑作ドキュメント。
「昭和史の語り部」が遺した、もうひとつの「日本のいちばん長い日」。精緻に記録された「開戦の日」
〈その安全のために、あるいは国益という名の打算行為から国家がなりふり構わず立ち上がることは、これからもありうるのである〉(「あとがき」より)
解説・砂川文次(芥川賞作家・元自衛官)
単行本 2001年7月 文藝春秋刊
旧版文庫 2003年12月 文春文庫刊
新装版文庫 2024年7月 文春文庫刊
【※この電子書籍は新装版文庫を底本としています。旧装版文庫を底本とした電子書籍(2014年4月配信)と本文内容は同一であり、新たに砂川文次さんによる解説を付したものです。】
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Sam
47
1941年12月8日の真珠湾奇襲攻撃に至るまでの外交交渉の内幕と開戦前後の推移を詳細に描いたもの。なんとなく近現代の歴史には食指が伸びないのだが本書は非常に興味深く読むことができた。読み手を引き付けるこの面白さは当時の各国首脳、軍人、新聞記事、さらには市井の人々(とはいっても評論家や作家だが)の多くの発言や日記、記録を巧みに引用したことによってその時代の空気感がありありと感じられるところにあると思うが、著者の歴史観に頷くところが多かったことももう一つの要因。「日本のいちばん長い日」も読まねばな。 2024/10/15
へくとぱすかる
39
「日本のいちばん長い日」以上の大冊で、読了までかなりの期間がかかった。ミレニアムの年に書かれた本だが、見事に太平洋戦争が始まった時代の空気を再現している。意外なことに開戦を熱烈に歓迎したのは国民の方で、半藤さんはこれを幕末以来の「攘夷」の続きとみている。太平洋をはさんでお互いに人種差別的な世論がぶつかり合っているさまを読むと、平和を確実にするには、政治家よりも、一般の人々の意識こそが重要だと思う。昭和初期からの日中戦争、あるいは半藤さんの著書にあるように日露戦争期にまで、その原因を遡る必要があるだろう。2024/08/31
りんだりん
19
1941年12月8日、日本軍は真珠湾を奇襲攻撃した。そこに至るまでの日米の外交交渉、駆け引きの内幕、そして「真珠湾の日」当日の24時間の詳細について、膨大な資料を時系列に整理して提示してくれている。日米それぞれの目線から、そして市井の人、ジャーナリスト、政治家、軍人、天皇などさまざまな人の目線から描くことで全体を立体的に捉えることができるようになっている。読んでいると、まるで自分がそこにいるかのようだ。世界がきな臭くなってきている昨今、今一度歴史から学ぶ時がきていると思う。★42024/07/30
ひめの
5
太平洋戦争の開幕、真珠湾攻撃の様子を時系列に沿って描く。前半は主に日米交渉の模様と作戦企画。中盤で攻撃のもよう。後半は日米の首脳、国民の雰囲気などが描かれる。ハル・ノートのミステリー、ルーズベルトの陰謀論、宣戦布告の通告の遅れ等様々か謎があり、それを考えるのも面白かった。また、多数の当時の回想文などを引用していて当時の雰囲気を伺えた。緻密に情報をとらえて書くことで、短絡的に◯◯が悪い、ではなく数々の人々の思惑と国民を雰囲気が開戦とそれに続く敗戦に突き進んで行ったのだなと感じた。2025/01/20
ビタミン
4
★★★★☆ 開戦と戦勝の報に接した際の一般庶民の大変なことになったという直感と、それを覆い隠そうとするかのような熱狂、当時米英に対し蓄積された想いを想像すると何とも言えない気持ちになると共に一種悲壮な感動を覚える気がする! 結局のところ政府や軍隊だけでなく、国レベルで引っ返せないところまで来ちゃってたんだろうなー。2025/03/18