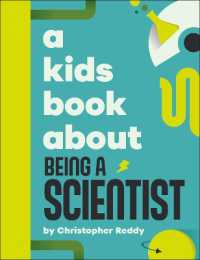内容説明
リーゼ・マイトナー、伊藤野枝、メイ・サートン、ヴァージニア・ウルフ、マルゴー・フランクとアンネ・フランク姉妹、湯浅年子…この女を見よ! 科学者、詩人、活動家、作家、スパイ、彫刻家etc.「歴史」の中で、おおく不当に不遇であった彼女たちの「仕事」がなければ、「いま」はありえなかった。彼女たちの横顔を拾い上げ、未来へとつないでいく、やさしくたけだけしい闘いの記録。
目次
はじめに/1 マルゴー・フランクとアンネ・フランク姉妹/2 伊藤野枝/3 シルヴィア・プラス/4 エミリー・デイヴィソンの葬列を組む女たち/5 ヴェルダ・マーヨ(長谷川テル)/6 ロザリンド・フランクリン/7 婉容/8 ブラック・イズ・ビューティフルを歌う女たち/9 マタ・ハリ/10 クララ・イマーヴァール/11 エミリー・ディキンスン/12 水曜日にその傍らに立ち続ける女たち/13 ヴァージニア・ウルフ/14 エウサピア・パラディーノ/15 マリア・スクウォドフスカ キュリー/16 ラジウム・ガールズ/17 湯浅年子/18 ミレヴァ・マリッチ/19 貞奴/20 学校へ通う少女たち/21 アンナ・アフマートヴァ/22 カミーユ・クローデル/23 高井としを/24 ヒロシマ・ガールズ/25 メイ・サートン/26 リーゼ・マイトナー/27 アストリッド・リンドグレーン/28 風船爆弾をつくった少女たち/おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fwhd8325
75
戦争というと「第二次世界大戦」のことと思ってしまうのですが、この戦争前も後も、世界では戦争が絶えたことはありません。その戦争において、声を上げられなかった、上げた声を封殺されてしまった歴史があります。その歴史はほとんどが女性によるものです。女性だから…それを考えると、それはいつから?何で?と疑問が浮かびます。その答えは見つかりません。短くまとめられたバランスのよい構成だと思います。2024/04/17
がらくたどん
60
薄くて可愛らしい本なんですよ。描かれるのは戦争の世紀のどこかで小さかったり大きかったりの名を遺してくれた女の子と女の子だった女性と女性達の28のエピソード。闘って負けた子もいれば「立派な仕事」の担い手なのに認められなかった子もいる。生活の千本ノックを必死に打ち返しているうちに才能が枯れてしまった子もいる。28枚の肖像画。みんな唇を結んでいる。そして考えている。「なんで?」って。置かれた境遇の精一杯を全うするのは美しい。でも、その立ち位置は後世に継承すべきものかは分からない。だから囁いて。ちゃんと聴くから。2024/12/26
ぐうぐう
44
女性というだけで虐げられてきた彼女達の記録。それを小林エリカは「戦争」と呼ぶが、ただ仕事をしようとし、ただ生きようとしただけなのに、女性にとっては闘いを強いられてしまう理不尽さが、その言葉には込められている。ロザリンド・フランクリンやマリ・キュリーといった、小林がこだわり続けてきた主題に関わる人物もいれば、エミリー・ディキンスンにヴァージニア・ウルフら文学者、あるいは婉容とマタ・ハリのような歴史の犠牲者、さらにラジウム・ガールズやヒロシマ・ガールズといった歴史に埋もれがちな人々をも(つづく)2024/04/16
hitomi
24
読売新聞の書評を読んで。戦争に巻き込まれた女性たちを紹介した本。伊藤野枝やヴァージニア・ウルフなど有名な人もいれば無名な人もいますが、一人ひとりが名前のある人間であることを忘れてはならないと思いました。良い本ですが、文章が読みにくくて困りました。主語を「男」「女」としている箇所が多く、誰を指すか分かりにくいところがありました。また、他項目への参照が多過ぎるので、もっと削ってよかったのでは?と思います。著者自身によるイラストは、不満を表した表情にインパクトがありますが、写真があっても良さそう。2024/06/23
かめりあうさぎ
22
初読み作者様。戦争に翻弄された女性たちの生涯をそれぞれ簡潔に描いた一冊。28章全126ページ。第一次・第二次世界大戦の頃は今より女性の選択肢も地位も低く、男性の始めた戦争に否応無しに巻き込まれ命や純潔を奪われたり、功績を盗まれたりが当たり前だったことがよく伝わってきました。割と感情的な筆致なので読み手は選びそう。エスペラント語という人工言語を初めて知りました。作家や詩人も多く紹介されているので彼女たちの著書を読んでみたいなと思いました。2024/06/08
-
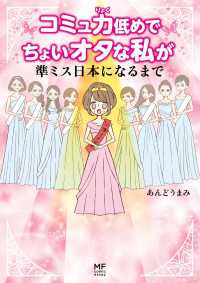
- 電子書籍
- コミュ力低めでちょいオタな私が準ミス日…