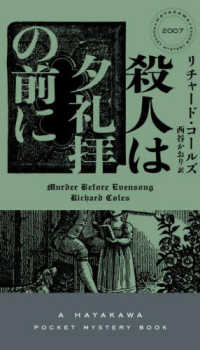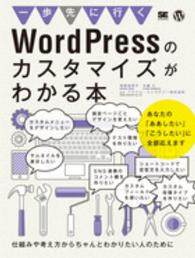内容説明
暴力を加える,強く叱責する…….保育施設において子どもの心身に対する深刻な被害が相次ぐ.いま保育の現場はどうなっているのか.長年,保育問題に取り組んできた著者が豊富な事例をもとに問題の背景を丹念に検証.保育の「質」を置き去りにした政策を問い,子どもが主体的に育つ環境づくりへ向けて具体的に提言する.
目次
はじめに
第1章 相次ぐ不適切保育の実態
裾野市の事件が照らし出した暗がり
見えているのは氷山の一角
保護者の立場からの要望
ブラックボックスになりがちな特性
「訴え」や「通報」が葬られる背景
保育は止められないライフライン
改めて不適切保育とは何か
全国保育士会のセルフチェックリスト
報道や「親の会」への相談でよく見られる事案
◆コラム1 保育施設の種類
◆コラム2 イギリスのDBS
◆コラム3 保育所保育指針
◆コラム4 指導監査とは
第2章 不適切保育の背景にあるもの――子どもが育つ場で何が?
不適切保育の背景をみる
園の保育観・理念という背景
「しつけ」「指導」という不適切保育
保育者の資質という背景
エスカレートする強者の行為
保育の質を左右する「風通し」とは
保育体制はなぜ「苦しい」のか
保護者が子どもを守るために
カメラ導入の是非
◆コラム5 子どもの権利委員会が示した「体罰禁止」の理念
第3章 子どもを見失った少子化対策――子どもの権利の視点から検証する
一・五七ショック
女性が働き続けられる社会へ
両立支援のための保育制度改革
「利用者ニーズ」という印籠
共働き一般化へ
無頓着な「詰め込み保育」はいまも続く
都心の園庭は「ぜいたく品」か?
週六六時間を週四〇時間労働の保育士が支える
気がつけば「長時間保育大国」
働き方改革の出遅れ
保育士という職業の位置づけ
「パート保育士活用」が打ち出される
「保育の市場化」をめぐる議論
◆コラム6 保育ママ
◆コラム7 二〇一四年に起きたベビーシッター事件
◆コラム8 子育て支援員
第4章 「保育の質」は社会の未来を左右する――子どもが育つということ
保育の質への無理解が制度を歪めた
子どもは安全と栄養だけでは育たない
アタッチメント理論は政策に活かされたか
保育者の専門性や経験値が必要とされる理由
三・四歳を六対一で保育したペリー・プリスクール
コロナ禍の調査から見える保育の実像
五歳児の調査結果について
三歳児の調査結果について
家庭の養育力と保育の質の関係
非認知スキルの育ちをどう支えるか
「早生まれ問題」に関する大人の責任
「習い事保育」は本当に付加価値なのか
有料サービス化による子どもの分断
質の高い保育は質の高い子育て支援を実現する
◆コラム9 子どもの安心感――発達心理学の理論から
◆コラム10 二一世紀出生児縦断調査
◆コラム11 保育環境評価スケール
第5章 不適切保育のない社会へ――子どもの育つ場をどう支えるか
「子どもの権利」がようやく表舞台に
一人一人を大切に育む時代
動き出した保育士配置の改善
徐々に進んできた処遇改善
改善分が保育士に確かに届くために
不正・不祥事の被害者は子ども
「見える化」は実現するのか
低迷する第三者評価制度
監査・評価制度の混線
保育の質と保育政策の関係
「子どもを真ん中に」施策をブラッシュアップする必要
「女子ども」を軽んずる社会からの脱皮
不適切保育防止から質の高い保育の実現へ
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
ネギっ子gen
けんとまん1007
そうたそ
でんすけ
-

- 洋書
- ALOISE