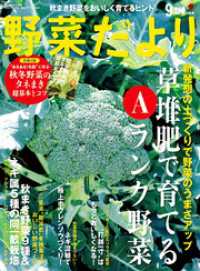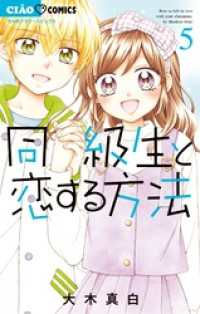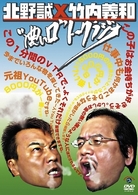内容説明
世界であいつぐ迫害や人権侵害.「自国第一」を掲げるポピュリズムの台頭.状況が年ごとに複雑になるなか,国際社会は葛藤を抱えつつも難民保護の取り組みを続けている.各国はいかなる論理と方法で受け入れを行なってきたのか.日本の課題は何か.政策研究の知見と実務経験をふまえ,多角的な視点で難民「問題」を考える.
目次
はじめに
第一章 難民はどう定義されてきたか――受け入れの歴史と論理――
国民国家体制と「難民」の誕生――第二次世界大戦まで
難民条約の成立
難民条約上の難民の定義
アフリカと中南米における広い難民の定義
戦争・武力紛争と難民
難民に準ずる別の地位を作ったEU諸国
難民受け入れ制度の空白地帯アジア
領土的庇護と外交的庇護
第二次世界大戦後にできた三つの重要な国際機関
移民と難民の違い
第二章 世界はいかに難民を受け入れているか――その1「待ち受け方式」――
自力でたどり着いた庇護申請者の難民認定審査
難民の集団的受け入れ――なぜ「途上国」は寛大なのか
国家間の保険制度としての難民保護
一時的保護
補完的保護
一時的保護と補完的保護の違い――EUの場合
第三章 世界はいかに難民を受け入れているか――その2「連れて来る方式」――
第三国定住とは
第三国定住での受け入れの流れ
「連れて来る方式」と「待ち受け方式」との違い
「待ち受け方式」と交換にされる第三国定住
難民以外の立場での受け入れ
民間スポンサーシップ
本国からの直接退避
第四章 日本は難民にどう向き合ってきたか
外国にいる難民支援のための財政的援助
インドシナ難民への対応――一九七五年から二〇〇五年
難民条約に基づく個別庇護審査――一九八二年から
なぜ日本の難民認定率は低いのか
第三国定住――二〇一〇年から
留学生としての受け入れ――二〇一六年から
アフガニスタン現地職員の退避――二〇二一年から
ウクライナ(避)難民の積極的受け入れ――二〇二二年から
第五章 難民は社会にとって「問題」なのか
難民はそもそも「エリート」
1 難民と犯罪
難民の定義から除外される場合
難民の追放が許可される場合
難民条約以外の国際法における送還停止規定
難民受け入れは「治安リスク」なのか
日本における外国人犯罪
2 難民受け入れによる財政負担
庇護申請者への公的支援
第三国定住難民のみへの公的支援
定住支援プログラムにかかる公的費用
難民を含む外国人と生活保護
第六章 なぜ「特に脆弱な難民」を積極的に受け入れるのか――北欧諸国の第三国定住政策――
スウェーデン、デンマーク、フィンランドの第三国定住政策の概要
なぜわざわざ「特に脆弱な難民」を受け入れてきたのか
近年のデンマーク、スウェーデン、フィンランドにおける変革
ノルウェイの第三国定住政策
なぜノルウェイだけ「パラダイム・シフト」が起きていないのか
ノルウェイの極右政党の戦略
政治交渉と妥協
人道性と定着可能性のバランス感覚
犯罪率の減少
世論による根強い支持と広範な理解
王室ファクター
おわりに
あとがき
主要参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
壱萬参仟縁
Satoshi
しゅー
tharaud