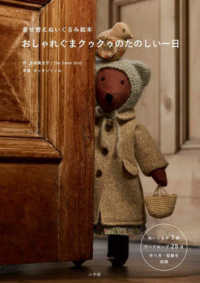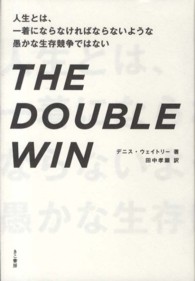内容説明
道具を使って文字を書く―。今日では当たり前の行為である筆記の文化は、いかに生まれ発展してきたのか。文字が持つ権威・宗教性・芸術性などの側面に触れつつ、文字の種類や記録法などの歴史を紹介。文字と同時に変化し日本へ伝播した筆・墨・硯・紙など、筆記具の造形や装飾に着目し、著者独自の実験も交えて描き出す、古代東アジアの文化史。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gorgeanalogue
12
著者専門の韓半島の考古学の知見は新鮮で参考になったし、文房具の様式や使用の考古学的研究によって得られる知見が書体や書風に与える影響・相互関係への指摘、また文房具の使用が国家の統治システムの発展と不可分であることなど、蒙を啓かれる個所も多かったが、文章、行論が何だか幼く、また文字文化についての著者の目配りは広いとはいえず、「面白い」とまではいかなかった。後半の古代文房具の「実験考古学」はこんなものか、という感じ。2024/07/14
さとうしん
12
いわゆる文房四宝だけでなく、広く文字使用のはじまりや書写行為そのものを対象としており、「文房具の考古学」というより「書写の考古学」と題した方が良さそうな内容。地域も中国と日本だけでなく、著者の専門らしい朝鮮半島の状況も大きく取り上げている。また、実験考古学的な試みもある。本書で大きく問題としているのは、文字、あるいは文房具(らしきもの)の登場・導入と普及とは異なるということである。これは書写行為にまつわるものだけでなく、たとえば鉄製兵器などの登場と普及についても同じことが言えるだろう。2024/06/26
hiro6636
4
文字らしきものが刻まれた、あるいは書かれた物体が出土すること=文字生活の証明ではなく文字を書くために付随する道具である文房具の存在が重要である。2025/06/01
河イルカ
3
図書館本 俗に文房四宝と呼ばれる筆紙墨硯を考古学的に分析して、進化の足跡をたどる本。 各道具の道具としての性質、考古学資料としての性質が丁寧に説明されていて、文字を書くことにどのような役割を持っていたのかが浮き彫りにされる。 そしてそれは、(東アジアの稀有な)文字文化にどのように貢献したかということでもある。 読了後は、筆紙墨硯がアンパンマンのキャラのように生き生きとしゃべりだす。2025/06/14
takao
1
ふむ2024/10/13