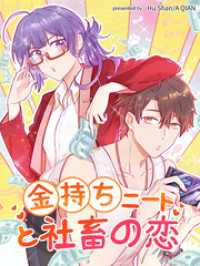内容説明
政府・自治体や企業から独立した民間の非営利団体・組織=NPO。阪神・淡路大震災後のボランティア活動以降、広く知られる。近年、子どもの貧困や孤独、気候変動など新たな社会課題が顕在化すると、行動の中心となり、活動分野と範囲を拡大。かつての会社や地域社会のような人と人を結び付ける「中間集団」が細るなか、その受け皿としても注目される。本書は、歴史、制度、存在理由から特性まで、把握しづらい実態を描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
逆丸カツハ
44
多分ないと思うが、自分の構想がうまく行けば組織を立ち上げたいと思うので手にとってみた。NPOは国家のものでも、市場経済の営利組織でも、家族などのコミュニティでもない、「ではない」という定義しづらい存在である。それは柄谷行人の交換様式論にそのままあてはまり、交換様式Dの領域に生まれるものではないかと思った(たぶん、交換様式論的にはAにすぐに回収されるということになるだろうが)。資本と国家の世界の次の世界がありうるとするなら、幾多ものNPOが生まれ消えていく世界なのかもしれない。2024/10/19
よっち
34
政府・自治体や企業から独立した民間の非営利団体組織NPO。その歴史、制度、存在理由から特性まで、把握しづらい実態を描いた1冊。阪神・淡路大震災後のボランティア活動後広く知られるようになり、子どもの貧困や孤独、気候変動など新たな社会課にも活動範囲を広げる多様な組織はどういう制度で、それ以前の市民による公益活動の歴史も振り返りながら、なぜNPOが必要なのかを解説していて、組織のあり方として難しい側面もあるようですが、政策だけではカバーしきれない部分を補っていく上で欠かせない存在となりつつあるのを実感しました。2024/07/30
かごむし
16
NPO(非営利組織)は、営利を目的とせず、社会的な課題に取り組む民間の組織である。災害ボランティアや地域の居場所提供、気候変動対策など多岐にわたる活動を行う。NPOは、サービスを供給する事業体としての顔と、社会全体に働きかける運動体としての顔を持ち、これらが相互に関連している。NPOの活動は、社会問題に対する挑戦であり、複数の利害関係者が関与するため、その運営は複雑である。しかし、NPOは社会と個人をつなぐ重要な役割を果たし、社会の強靭性を高める存在である。2024/11/27
makoto018
14
NPO法人を改めて学習。阪神・淡路大震災のボランティア元年からの誕生の経緯、NPO法の解説や実態などを最新データで学べた。世界(欧米中韓)と逆で、日本では政府や大企業に較べてNPOの信頼度が低く、寄附意識も薄いこと。一見、NPOは日本の土壌に馴染まないようだが、江戸期の互助組織や救貧思想など、戦時翼賛体制前の日本は市民活動、公益意識が強かったとわかる。家族、地域の変容と雇用の流動化で、中流層が存在しなくなった日本。社会課題に寄り添い、他者の問題を理解し、それぞれが参加する場としてNPOは現実解となりうる。2024/08/12
owlsoul
9
阪神淡路大震災において、自らの意志で被災地に赴いたボランティアによる支援活動は、政府の初動の遅さと対比され大きな注目を浴びた。その後、法整備が行われNPOという名称が認知されていく。意欲ある人々が率先して動き、現場での実践から見えてくる問題を社会にフィードバックする。NPO特有の柔軟性は、政治や経済の隙間を埋める一助となるが、その強みは裏返って弱さともなる。意欲による動員は維持継続が難しく、需要と供給のミスマッチを生みやすい。自由参加はガバナンスや技能の問題を孕む。自己実現に絡む現代の組織論として興味深い2024/11/30