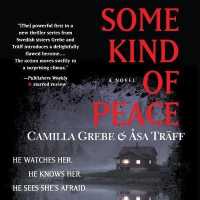内容説明
『具体と抽象』から10年。満を持して、シリーズ第4弾刊行!
「ある型」の思考回路は、「あるもの」に目を向ける。
「ない型」の思考回路は、「ないもの」も視野に入れる。
その両者の圧倒的ギャップが世の中を動かしている。
そのメカニズムとは?
私たちの「ものの見方」には、突き詰めれば大きく二つのタイプ、すなわち「ある型」思考と「ない型」思考がある。この両者間の「ギャップや認知の歪み」が世界を動かしている……と著者は説きます。
本書では、「世の中そう簡単に二択で表現できるものではない」という疑問にも丁寧に答えながら、「二つの思考回路」が織りなすギャップや衝突のメカニズムをひも解きます。そこからは、私たちが世の中の事象に対して抱くモヤモヤ感を晴らすヒントが見えてきます。
【著者】
細谷功
著述家、ビジネスコンサルタント。1964年、神奈川県に生まれる。東京大学工学部を卒業後、東芝を経てビジネスコンサルティングの世界へ。アーンスト&ヤング、キャップジェミニ、クニエなどの米仏日系コンサルティング会社を経て独立。問題解決や思考に関する講演やセミナーを企業や各種団体、大学に対して行っている。
著書に、『地頭力を鍛える』『アナロジー思考』(以上、東洋経済新報社)、『メタ思考トレーニング』(PHPビジネス新書)、『具体と抽象』『「無理」の構造』『自己矛盾劇場』(以上、dZERO)などがある。
目次
序 章 歪みとギャップが世の中を動かしている
第1章 「答えがある」と「答えがない」
第2章 問題解決と問題発見
第3章 カイゼンとイノベーション
第4章 レッドオーシャンとブルーオーシャン
第5章 具体と抽象
第6章 魚と釣り方
第7章 自分と他人
第8章 「同じ」と「違う」
第9章 安定と変化
第10章 守りと攻め
第11章 受動と能動
第12章 ツッコミとボケ
第13章 常識と非常識
第14章 内と外
第15章 閉と開
第16章 部分と全体
第17章 既知と未知
終 章 「無の境地」とは何か
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MI
ta_chanko
江口 浩平@教育委員会
こうの
もず