内容説明
大河ドラマ「光る君へ」の時代考証者が描く平安期の天皇・貴族の統治と人事の実態。「御遺誡(ごゆかい)」と呼ばれる史料には権力の座に君臨した人物たちの帝王学や宮廷政治の心得、人物批評が克明につづられている。宇多天皇、醍醐天皇、藤原師輔、菅原道真の四つの文書から中世に向かう時代変遷や個性を描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
33
近年、平安時代の皇位や摂関の継承、時代の深層に迫る史料として注目されている「御遺誡」。「光る君へ」の時代考証を務める著者が5つの御遺誡を通して案内する一冊。遺詔や遺言とは異なり、多くは子孫や門下などの後人に遺した訓戒で、嵯峨天皇、宇多天皇、菅原道真、醍醐天皇、藤原師輔の遺した御遺誡から、天皇や大臣が己の命より大事にしたものとは何か、子孫や門下に何を遺そうとしたのか、皇統確立や摂関家成立の関係とを考察していて、思いがけず嫡流になった時代背景も少なからず影響していたのではという分析はなかなか興味深かったです。2024/07/07
Toska
12
24年6月出版で今年の大河を当て込んだことは間違いなく、内容も少し急いだ印象(引用が多く本文は意外に少ない)。だがそれでこのクオリティを保っているのは流石だし、平安朝にスポットが当たる機会などそうそうないから全力を傾けるのも分かる。この著者は研究対象への愛情を隠さないタイプ。子孫のために「御遺誡」を残したのは天皇家や摂関家の中でも傍流から嫡流に成り上がった代の当主が多い、という結論が興味深い。いわゆる万世一系理念も、こうした歴史的経緯を踏まえて考える必要があるだろう。2024/11/01
石光 真
3
遺誡を遺したのは宇多天皇、醍醐天皇、藤原師輔、いずれも本来嫡流でなかったのに新たに嫡流になりつつある人物による。源氏だった宇多、醍醐、摂関でなかった師輔の謙虚さが読み取れる。師輔は息子の伊尹、兼通、兼家、孫の道隆、道兼、道長の兄弟争いや傲慢を予測して坐しめた如くであると倉本一宏は言う。2025/02/04
時雨
3
子孫や門人など後人に遺された訓戒を「遺誡(ゆいかい)」という。帝の譲位や公家の家督相続に先立って、作成者が元気なうちに作成される点が遺言(遺詔)とは異なり、作成者自身の職務内容に触れるものも少なくないことから、後継者に宛てた引き継ぎ文書の色彩が濃い。現代まで伝わる遺誡のうち、本書では嵯峨天皇の『嵯峨遺誡』、宇多天皇の『寛平御遺誡』、菅原道真の『菅家遺誡』、醍醐天皇の『延喜御遺誡』、藤原師輔の『九条右丞相遺誡』を取り上げて、史料の信憑性を吟味しながら平安貴族の政治劇の舞台裏を垣間見る。2024年6月初版。2024/09/30
読書記録(2018/10~)
0
「おわりに」で嫡流外からあらたな嫡流となった人物が遺誡をのこす、という話、さもありなん。個人的には師輔の章が面白かった。時折入る著者のツッコミに笑ってしまう。2025/09/24
-
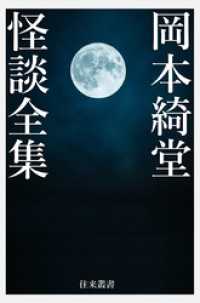
- 電子書籍
- 岡本綺堂怪談全集 往来文庫
-
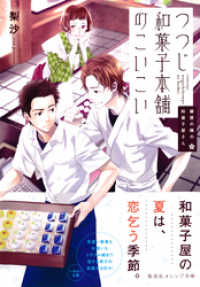
- 電子書籍
- 鍵屋の隣の和菓子屋さん つつじ和菓子本…







