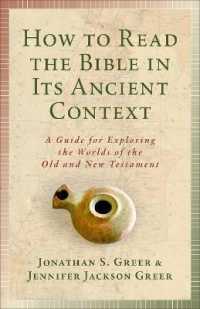内容説明
コロナ禍が収束し、各地に観光客が戻ってきたことで再び表面化しているオーバーツーリズム問題。
・市民が市バスに乗れない京都
・登山道に行列ができる富士山
・違法駐車とサンゴ劣化に悩まされる沖縄
・「行列店」が増えすぎている東京
……など、自然環境や地域住民の生活が脅かされる事態が多発しています。
今後も旅の楽しみ、喜びを守るためにはどうすればよいのか、ユネスコ本部で在外研究を行い、多数の論文を執筆している気鋭の研究者が、国内外の豊富な事例とともに解説します。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おせきはん
27
オーバーツーリズムの現状と改善策について、国内外の事例を踏まえて論じています。島のようにアクセス手段が限られていて、住民の生活の場と離れた観光地であれば、比較的コントロールできる可能性は高そうですが、そうではない観光地が多いのが実情です。マナーや良心に訴えるだけでなく、地域の生活を維持するために観光客に応分の負担を求めつつ、負担に見合う質の高いサービスを観光客に提供するとともに、訪れる場所・時期・時間帯をいかに平準化させるかが重要ではないかと思いました。2024/09/07
スプリント
6
オーバツーリズムが発生する背景とその抑制策を説明。 海外での成功事例も紹介しており世界的なオーバツーリズムの現状と対策を知ることができる。2024/08/14
つかず8
5
オーバーツーリズムをテーマに、観光の経済効果と地域負担のバランスを取るための具体策を提案した一冊。観光客数の分散、訪問人数制限、課税による環境保全などが挙げられ、住民や事業者、行政の協力の重要性も強調されています。法や制度の不備や国立公園の保護不足、日本特有のモラル頼みの限界についても言及。成功事例やエコツーリズムの実践例を交え、観光客自身が選択を見直す意識改革が必要だと示唆しています。2024/11/26
お抹茶
4
日本では法や制度によらずに良識やモラルや思いやりによって秩序を形成するが,外国人観光客も同じとは限らず,法や規定にないことに頼るべきではない。沖縄は観光客の数に注力するが,平均消費額はハワイの3分の1で,オーバーツーリズムの問題は深刻。規制的手法や宿泊税は利害関係者との合意形成が難しい。美しい場所にマナー啓発ポスターや看板をたくさん立てるのは国際的な感覚からは奇異に映る。国立公園の保護を国はできていない。観光客として,認定ガイドや地域の良いものを選ぶのがオーバーツーリズム抑制に効果的。成功事例も紹介。2024/07/18
Go Extreme
2
https://claude.ai/public/artifacts/647d0cd1-dd82-4e9b-9e0f-31ea75c51bd6 2025/07/06