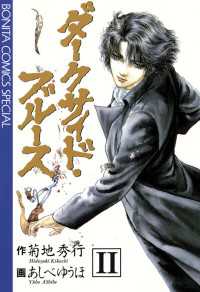内容説明
◆◇自由に生きるって、こういうことなんだぜ!◇◆
儒教の権威が失墜し、政治社会が揺れ動くアナーキーな魏晋時代、自由闊達な思想が炸裂した!
詩を詠み、議論を戦わせ、楽器をかき鳴らし、そして心ゆくまで痛飲し、葛藤を抱えながら己の思想を貫こうとした彼ら。
権力に睨まれ刑死した者あり、敢えて世俗にまみれた者あり、いずれも激烈に生きたその群像を、シャープな筆致で簡明に描ききる!
中国史、中国思想に興味のあるものならば、「竹林の七賢」と彼らがおこなった「清談」というものについて、強い印象がのこっているだろう。
しかしながら、彼らがどのような背景をもつ思想家で、どのような知的交流をしたのか、具体的なことを知っているだろうか?
政治・社会が流動し価値観が変わりゆく時代にあって、それぞれの切実さをもって己の思想を生きた彼らは、いずれも「世俗を離れた、純粋な知的探求者」という一面的な見方ではとうてい捉えきれない思想家たちであった―
彼らの人間くさい生き様と、為した仕事のエッセンスを知る、とてもコンパクトで、楽しい一冊。
【本書「はしがき」より】
七人の人物が「竹林の七賢」という一つのグループにまとめられはしたものの、そのなかにはさまざまのタイプの人間が含まれていて実に個性豊かである。それだけではなく、一人の人間についても、その性向と行動とが一見すると矛盾するかのように思われる場合すらないではない。その点においてもまた、儒教が唯一絶対の価値の源泉であった漢代とは異なって、価値が多様化した魏晋の時代の一つの指標をみとめることができるのだが、「竹林の七賢」の面々は、ある場合には文学作品や哲学論文によって、ある場合にはそのライフ・スタイルによって、それぞれに強烈でしたたかな自己主張を行なったのである。
*本書の原本は、1996年に『風呂で読む 竹林の七賢』として世界思想社より刊行されました。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
niisun
ひよピパパ
kuroma831
大先生
電羊齋