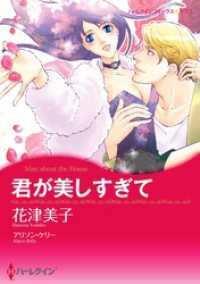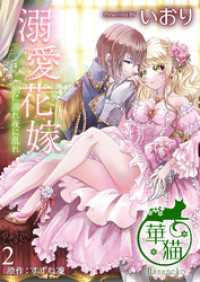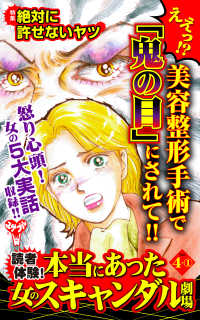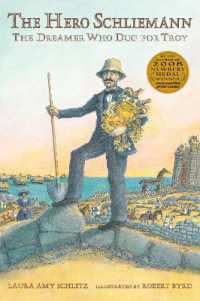- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
判定は正しくて当然、間違えれば袋叩き!
どんなスポーツ競技にも必要な「審判員」。彼らがいなければ勝負判定も採点もできず、競技の公平性は担保されない。
重要な役割を任され、絶大な権限を与えられる審判員だが、そのジャッジは正しくて当たり前、「誤審」しようものなら猛烈な批判を浴びる。近年は映像判定をはじめとする「機械」に仕事を奪われつつあり、“競技の番人”としての「権威」「威厳」も低下している。
それでも彼らはなぜ「ジャッジマン」としてスポーツに身を捧げるのか。
日本人として初めてW杯の開幕戦で主審を務めた西村雄一(サッカー)、公式戦3000試合出場の橘高淳(プロ野球)、行司の最高峰である第37代木村庄之助を務めた畠山三郎(大相撲)ほか、第一線で活躍した8競技の審判のインタビューをもとに構成。
彼らが「審判」を目指した理由、自身の「誤審」を巡る騒動、機械判定に対する複雑な思い--競技ごとに異なる判定の難しさとともに「審判としての誇り」を語る。
また、「世界的に物議を醸したW杯開幕戦のPK判定」(西村)、「巨人・ガルベスの硬球投げつけ事件」(橘高)など、審判員として関わった「騒動・事件の裏側」も初めて明かされる。
(底本 2024年5月発売作品)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
hiace9000
108
剣道審判経験者です。本書でインタビューを得たどの競技に自身が一番共感できるのだろうか…、その視点での読み。サッカー、プロ野球、アマチュア野球、柔道、ボクシング、水泳飛び込み、ゴルフ、大相撲の各界トップ審判の方々の談話はそのスポーツその競技の魅力を何倍にも増してくれる、珠玉の逸話揃い。中でも大相撲の立行司の世界は初耳学のオンパレード。相撲の場所が始まると17時以降は気もそぞろな人間の一人として、トリビアルなネタはもはや感動もの。で、一番の共感競技は意外やサッカー。審判は"マネジメント"!まさにそこなのです。2024/09/10
yuni
39
題名を見て「アーーーイ!」で有名なあの球審を思い浮かべた野球バカです。本書によると派手なパフォーマンスをするのは自信の表れだそう笑。邪な気持ちで手に取ったけれど意外にも考える読書となりました。特に印象に残ったことが2点。1つは柔道。強い選手でないと分からない駆け引きに審判の質が追いついていないこと。これはパリ五輪をみても明らかです。もう1つは水泳の飛び込み。審判のえこひいきが常習化しているとのこと。どの採点競技にも言えますが個人の好みで採点すると悲劇が生まれます。審判達の本音と競技に対する愛を感じる1冊。2024/10/17
Eric
20
スポーツが異なれば、審判に求められる役割も大きく違う。各スポーツの特徴や誤審を巡るストーリー、ビデオ判定の導入に対する意見など、色々な切り口からあるべき審判像を語る。一流選手が審判になるケースと最初から審判を志すケース、また選手よりも審判の方が輝くケースなど様々。あとは審判の人手不足が印象的。審判がちゃんとできる人は結構な頻度にて駆り出されるが、低賃金またはボランティア、かつ体力的にもきつい場面が多い。それでも時間を捻出するのは、今まで深く関わってきたスポーツへの愛ゆえだろう。2024/09/07
おいしゃん
19
ゴルフや相撲、はたまた飛び込みなど、ふだん馴染みの薄い競技でも、それぞれ審判がどのように黒子に徹しているのかがとても興味深かった。2024/07/01
おくちゃん
10
色々なスポーツの審判の方々のお話。今度から違う視点でスポーツを観ることがてきそうです。筆者との対談でしたが、審判の方同士の座談会も面白いかも。2025/01/12