内容説明
熊本の高等学校を卒業して、東京の大学に入学した小川三四郎は、見る物聞く物の総てが目新しい世界の中で、自由気儘な都会の女性里見美禰子に出会い、彼女に強く惹かれてゆく……。青春の一時期において誰もが経験する、学問、友情、恋愛への不安や戸惑いを、三四郎の恋愛から失恋に至る過程の中に描いて『それから』『門』に続く三部作の序曲をなす作品である。(解説・柄谷行人)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
646
明治40年の東京、あるいはその頃に地方から上京して東京帝国大学に入学した三四郎のような境遇の青年たちの気概はよく伝わってくる。ただ、主人公の三四郎にしても美禰子にしても、近代的な自我の萌芽はあるものの、結局は自分自身がどうしていいのかはわからない。そのことは美禰子が三四郎に語る「ストレイ・シープ」に象徴されている。美禰子は三四郎に想いを寄せていたのだろうが、それもまた彼女自身にも確信できないままだったに違いない。「青春を信じない」漱石の青春小説に明確な指針や解答はないし、だからこそ続編が必要だったのだ。2012/10/07
Major
388
僕個人としては、美穪子という女性は『三四郎』の文中でも書かれている通り(三四郎の見解)第三の世界に住まう住人でありながらも、美穪子自身はこの3つの世界にまたがって住まうと考えているのだと僕は思う。ということは、漱石がそのように考えて造形した女性だということも言えよう。そこに、そこはかとない頼りなさげな(=憐れな)第二の美しさ(第一の美しさは、言わずもがなのあの凛とした『草枕』の那美にも見られた近代的知的女性の美しさ)を僕は観る。(コメントへ続く)2015/01/03
夜間飛行
379
昔を思い出す青春小説だがそれだけではない。三四郎は相宿になった女から別れ際に「余つ程度胸のない方ですね」といわれ狼狽える。これは素のままで自由に振る舞えない人間の困惑だ。やがて彼の前に美禰子が現れる。何度も空を見あげる美禰子を介して三四郎は人間の謎に向き合う。美禰子は自分を愚弄しているのか、気があるのか。本郷の通りを二人で歩く時、三四郎は美禰子の兄の許可を得ていないことを気にする。通行人の視線が刺さる。そんな時代なのだ。皆何かに囚われている。それでもやはり青春の美しい話を読むと、無条件で涙が出そうになる。2023/12/29
まさにい
372
漱石が小説を書き始めたのが、38歳。三四郎を書いたのが、41歳。明治41年であった。東京はまだ、西洋文明・文化の配電盤(司馬遼太郎氏の表現)、東京大学はまさに配電盤そのもにだったのだろう。帝大生の三四郎の話は、文学論、美術論、科学論、東京の学生の実態として、この小説により全国に知られたのかもしれず、この小説が配電盤の内容として、理解されることは漱石も意識していたものだと思われる。同時代に自分が地方でこの小説を高等学校の学生として読んだらどのように思ったのだろう。はたして、東京にあこがれを持ったのか…。2016/09/16
ehirano1
354
3部作の初っ端。漱石お得意(?)の「時代の変化(≒価値観の変化)における一青年の恋愛」についての作品として捉えました。本作の舞台は明治ですが、「時代の変化(≒価値観の変化)」は普遍的に起こることから、我々は皆否応なく「時代の変化(≒価値観の変化)」に曝されます。その意味で、本作が時代を超えて読み継がれる理由が改めて良く分かりました。2024/11/16
-

- 電子書籍
- ないしょの未来日記 #1 恋愛ギライな…
-
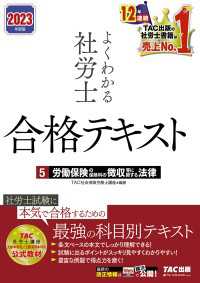
- 電子書籍
- 2023年度版 よくわかる社労士 合格…
-

- 電子書籍
- お狐様の異類婚姻譚: 3【電子限定描き…
-

- 電子書籍
- キャットニップ 3.
-
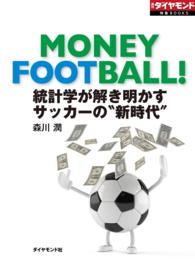
- 電子書籍
- 統計学が解き明かす サッカーの“新時代…




