内容説明
80代から90代の大台へと足を踏み入れた作家がつづる日常。少しずつ縮む散歩の距離、少量の水にむせる苦しさ、朝ぼんやりと過ごす時間の感覚など、自身に起きる変化を見つめる。移りゆく社会を横目に「ファックス止り」の自分をなぐさめ、暗証番号を忘れて途方に暮れ……。一方、年長者が背筋を伸ばしてスピーチを聞く姿に爽快感を覚え、電車の乗客の「スマホ率」など新発見も。老いと向き合い見えたこと、考えたこと。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
まふ
110
話題の本。読売で時々読んでいたが、まともに読むのは初めて。92歳になんなんとするのに立派な文章を書くそのプロ根性が素晴らしい。捧腹絶倒というわけにはいかないが、しっかりとガンバッテ生きていることそのものがエラクもあり微笑ましい。わが身を振り返った場合…いや、振り返るのはよそう。最近では90代がほぼ平均年齢のような勢いである。とどまるところを知らない我が国の平均寿命、喜ばしいのか恐ろしいことなのかワタシにはわかりません。2024/10/12
じいじ
80
じいじ83歳、いまも健筆を揮われている黒井千次さんの著書をとおして、たくさんの「元気」を頂いています。「老い」と言うこと、私は80歳になった3年前から折に触れて実感することが増えました。「居眠りは年寄りの自然…」と言う黒井さんの言葉に安堵しています。90歳を超えた氏は「健康維持のために1日最低20分は歩く…」を未だに実行している、とのこと。コロナ禍を言い訳に、ズボラをしている私は耳が痛いです。2024/08/19
どんぐり
77
老後像に深みをもたらす90代となった老作家のエッセイ56篇。老いに向かいつつある自分にも認識できる話が多い。たとえばこうだ。椅子から立ち上がろうとする時、その椅子の尻をおろしている面が低いと立つのに苦労する〈起立ゴッコを監視する眼〉。これはまだ早いかもしれないけれど、未知の若い女性たちと言葉を交わす機会が滅多になくなった〈入院生活の小さな救い〉。歩く範囲が狭くなり途中で腰をおろして休める場所を探す〈西日に感じた宇宙〉。転倒のほとんどが行事で、深刻な出来事となる〈行事か事件か、転倒問題〉。→2025/05/07
涼
64
http://naym1.cocolog-nifty.com/tetsuya/2025/07/post-b25d0c.html いよいよ大台に乗られたが、元気に毎日散歩に出かけていらっしゃいます。 しかし本書の途中からは、杖がお供に付くようになりました。2025/07/14
やまはるか
33
90歳過ぎた作家が老いについて綴った本書に期待したのは老いをどのように実感し、どう理解しているか、老いとは何かである。元気な高齢者をみて「あの人の動きは、実は老い損なったことを示しているのではあるまいか」と考えずにいられない誘惑を覚え「90代にかかって初めて老いは日常のもの、普通のもの、散文的なものへと変化し、人を最後の地点まで運んでくれるものへと準備を始めているのかもしれない」「老いは単なる時間の量的表現ではなく、人が生き続ける姿勢そのものの質的表現でもある」知りたかったことがそれなりに表現されている。2025/01/22
-
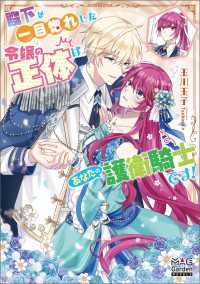
- 電子書籍
- 殿下が一目惚れした令嬢の正体はあなたの…
-

- 電子書籍
- 建築都市分野におけるカーボン・トレーデ…
-
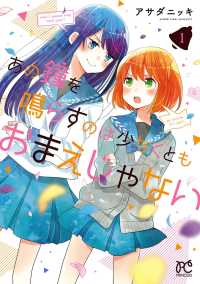
- 電子書籍
- あの鐘を鳴らすのは少なくともおまえじゃ…
-
![GOETHE[ゲーテ] 2018年4月号 GOETHE](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0521751.jpg)
- 電子書籍
- GOETHE[ゲーテ] 2018年4月…





