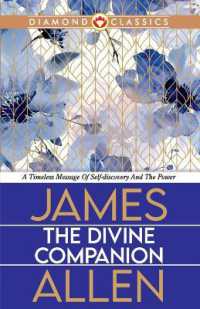内容説明
年々増え続ける不登校問題に、親は、学校は、社会は、子供たちとどう向きあえばいいのか。気鋭の心理学者がその解決策を探っていく。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
46
時代と共に不登校の概念も、変わり続けている。その時の指向性による部分も多い。今の状況を知り、その概念の広さと、人数の多さに驚きを隠せない。また、予備軍も多い。確かに、教育の機会をいかに提供するのかということで、いろいろな形態があるのは好ましい。ただ、そこに流れてしまう傾向があることが気がかり。特に興味深いのが、何年・何十年という追跡調査の結果。時代の風潮でもある、短期的思考の結果は好ましい結果を生みにくいということ。一見、恵まれた環境は、実は、そうでもないということを念頭に置くこと。2024/07/24
katoyann
17
心理学者による考察だが、読者層をどこに置いて書いているのかが不明瞭である。少なくとも当事者性はなく、不登校を非認知的能力の欠如という観点から考察しているが、事例分析もなく、持論に都合の良い文献を恣意的に用いて印象論を述べているだけで、はっきり言ってエッセイとしか思いようがない。学校に行くべきだという前提から話がされて、行かない子どもの非認知能力が言挙げされるときには、子どもの権利というのは考慮されていないと推察される。2024/10/19
てくてく
7
少子化、また、不登校の定義の関係で、保健室登校や連続で欠席しているわけではない場合は不登校にカウントされていないにもかかわらず、不登校の数は増え続けている。その最近の不登校の原因などを分析し、どうあるべきか考察している。学校での生活からでしか学べないものもあることを前提としながらも、本人および周囲の人たちが現状からどう脱出すべきかについてもいくつか提示されており、勉強になった。2024/07/07
安藤 未空
4
研究者が不登校研究について書いた本、というよりは研究者が既存調査や文献をベースに不登校に関する幅広く読みやすい内容を書いた本、という印象だった。引用を用いることで根拠はあげられていたが、全体的に著者の私見が多い印象だった。ただ、幅広く不登校について扱ってくれているので、昨今の不登校をめぐる状況を総合的に「何となく把握できたかな」という感想を持った。 教育機会確保法の成立は良いが、同時に文部科学省が学校の意義を改めて示すべきだったのではないか。この点が一番、示唆深かったように感じた。2025/09/03
takao
4
ふむ2024/06/16