内容説明
生命を賭して一対一で戦い、その結果にしたがって紛争を決着した「決闘裁判」。中世ヨーロッパに広く普及したこの裁判は、どのように行われ、いかにして終焉を迎えたのか。決闘裁判は、熱湯神判、冷水神判といった神判が禁止された以後も、1819年にイギリスで廃止されるまで存続した。それはなぜか。著者は、解決を他者に任せない自力救済の要素に、現代にまで通じる「当事者主義」の法精神をみる。法とは何か、権利や自由、名誉や正義とはどんなものかといった深い問いを投げかける法制史の名著に、「法と身体のパフォーマンス」を増補した決定版。
目次
プロローグ 『ローエングリン』──神の裁きとしての決闘/ルートヴィヒ二世/ワーグナーの『ローエングリン』/『ローエングリン』の持つ意味/オルトルートとは誰か/「神の裁き」/ワーグナーの狙い/神判と決闘裁判/第一章 神判──火と水の奇跡と一騎討ちモノマキア/中世ヨーロッパではいかに自らの無実を証明したか/自己中心的世界認識/神の奇跡/戦争という神判/キリスト教以前の神判/宣誓と神判/ゲルマン人はキリスト教化し、キリスト教もゲルマン化する/神判の拡大/熱湯神判/熱鉄神判/『トリスタンとイズー』/鋤の刃神判──聖女クニグンデ/冷水神判/決闘裁判/十字架神判と聖餐神判/神判の起源/ピーター・ブラウンの説──神判はなぜ世界中に存在したか/合理と非合理/「聖俗分離革命」/第四回ラテラーノ公会議/第二章 決闘裁判──力と神意/自力+他力/ダビデとゴリアテ/ローマ帝国の決闘裁判/グンドバッド王/一騎討ちによる決着/フランク王国に決闘裁判はあったか/なぜ「サリカ法典」は決闘裁判にふれていないのか/「リブアリア法典」/自由人の感性/決闘への懐疑/リウトプランド王の嘆き/カール大帝/フルリーの訴訟──修道院の間の決闘/神聖ローマ帝国皇帝オットー一世/オットー二世/正当防衛を証明するための決闘裁判/『ローランの歌』/判決非難/神よ、正義に光あらしめ給え/勝者を正当化する神判/自力救済の残酷/第三章 決闘裁判はどのように行われたか──賢明な仕方で運用される愚かなこと/決闘裁判はどのように行われたか/決闘裁判の三つの型/宣誓補助者や証人との決闘/誰が決闘できたのか/代わって戦う者/代理される者の拡大/決闘士とは/差別された決闘士/手を切断された決闘士/決闘士の収入/決闘の作法/決闘の保証/決闘場/牢に閉じ込められる原告と被告/決闘のいでたち/フェア・プレイの精神/勝者と敗者/和解とは何か/賢明な仕方で運用される愚かなこと/第四章 決闘裁判の終焉と自由主義/教会の禁令/王の力と封建制/決闘を嫌った都市の市民/ドゥ・カルーズュ対ルグリ/フランス最後の決闘裁判/決闘裁判がもっとも長く残ったイングランド/エリザベス一世時代の決闘裁判/共犯者告発人/ホワイトホーン対フィッシャー/陪審制の誕生/謀殺私訴/ボストン茶会事件/タイバーン荘の悲劇/アシュフォード対ソーントン事件/手袋を拾うか/決闘裁判の公式かつ法的な廃止/決闘裁判はなぜ存在したのか/自由と名誉の精神/名誉は権利と不可分である/権利のための闘争/エピローグ 正義と裁判/アメリカと中世ヨーロッパ/裁判国事主義/当事者主義とは何か/シンプソン裁判/私戦の代用としての裁判/当事者主義の原風景/欧米世界の光と陰/増補 法と身体のパフォーマンス/あとがき/文庫版あとがき/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
塩崎ツトム
MUNEKAZ
素人
Jampoo
-
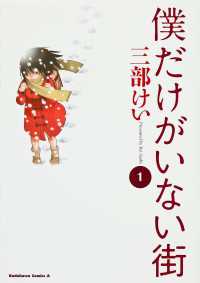
- 電子書籍
- 僕だけがいない街【タテスク】 Chap…
-
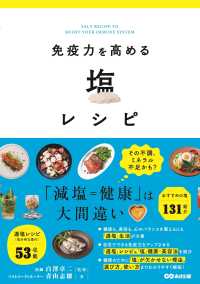
- 和書
- 免疫力を高める塩レシピ


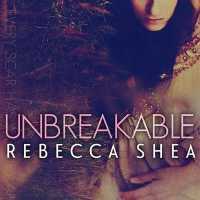
![大風水<ノーカット版>コンパクトDVD-BOX2<本格時代劇セレクション>[期間限定スペシャルプライス版]](../images/goods/ar/web/vimgdata/4988013/4988013496385.jpg)



