- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
明治時代に国を挙げて西洋化に突き進むなか、 日本美術の発展に功績を残した岡倉天心(1863‐1913)。ボストン美術館中国・日本美術部の責任者として、 東洋の美術を欧米に紹介し、1906年刊行のTHE BOOK OF TEA(『茶の本』)が全米ベストセラーとなったことで国際的に知られる。 岡倉天心の曾孫であり、近現代の国際関係史を専門とする著者が、国際文化交流の見地から『茶の本』をこれまでに知られていなかった視点をふんだんに盛り込んで徹底解説する決定版入門書。
目次
はじめに/二〇二三年の代表的日本人/芸術文化のチャレンジャーとしての天心/『茶の本』をどう読むか──筆者の視点/本書の構成/序章 『茶の本』の世界/1 『茶の本』が問いかけるもの/私の名前はOKAKURA Kakasuではない/The Book of Teaとその評価/ボストン茶会事件/原書初版装丁について/The Book of Teaの翻訳について/私と『茶の本』/『東洋の理想』『日本の覚醒』、そして『茶の本』/『茶の本』の翻訳はなぜ遅れたのか/The Book of Teaの代表的邦訳/天心と法隆寺/法隆寺・金堂壁画の修復/2 現代社会と『茶の本』/明治は遠くなりにけり?/岡倉家の茶の湯こぼれ話/天心の創作活動における四つの特質/3 『茶の本』成立の背景/親友の死に寄せた天心の漢詩/ウィリアム・ジェイムズが取り持つ縁/岡倉由三郎/蒟蒻問答にみる英語力/藤原定家の古歌/The Book of TeaとThe Ideals of the Eastの連続性/日本文化の発信に向けて/第一章 『茶の本』は「茶の湯」の経典か/1 岡倉覚三天心の生涯と『茶の本』/東京大学入学式総長挨拶/内村鑑三『代表的日本人』/新渡戸稲造『東西相触れて』/覚三の幼少期/幕末の志士たちと天心/2 天心の思想的背景/五浦に六角堂を建立/草堂としての六角堂/茶室は人生という荒野におけるオアシス/六角堂への思い──タオ(道)とは永遠の生成である/天心とDemocracy/一碗のお茶の中に平和が/ビゲロウと天心/ヘーゲルの東洋専制主義の呪縛/中江兆民『三酔人経綸問答』/真の文明国の姿とは/The Awakening of Japanを刊行/3 『茶の本』を読んだ人々/ウォーナーとThe Book of Tea/八杉直とThe Book of Tea/矢代幸雄とThe Book of Tea/南博『日本人論』と「茶の湯」/英語教材としての『茶の本』/林芙美子と『茶の本』/松岡正剛と『茶の本』/大岡信と『茶の本』/山口静一「天心が伝えた日本人の美意識」/橋本麻里「滾りたる茶」/4 「茶の湯」をめぐる考察/「茶人」は環境の思想家/タゴールと「茶の湯」/モラエス『茶の文化』/第二章 宗教と哲学から『茶の本』を読む/1 『茶の本』刊行一〇〇周年記念行事/ワタリウム美術館『岡倉天心展』/The Book of Tea出版一〇〇周年記念展(フリーア美術館)/2 アメリカにおける日本文化の受容/一八八三年のガードナー夫妻とモースの茶道体験/皮肉屋ヘンリー・アダムズの「茶の湯」評価/Willows Ladies(柳婦人会)の談話/差別を生んだ分類の歴史/ハーバート・リードの美術教育論/3 日本文化をめぐる論争/芸術は自由の領域/活け花論争──天心にとって「花」とは/編集者ジョンソン、出版社との関係/『茶の本』の成立事情/ボストン美術館と茶室/4 『茶の本』の構成/各章のタイトルと邦訳の異同/第一章 The Cup of Humanity──茶碗か盃か? 人情か人間性か?/日本はいつが野蛮であったか/「東と西は岡倉によって相逢った」/『茶の本』は対話の書か、それとも反逆の書か/第三章 文学・演劇にみるユーモリスト/1 The Cup of Humanity「人情の碗」/シェイクスピアの「パロディー」/チェンバレン『日本事物誌』と『茶の本』/ドナルド・キーンと『茶の本』/『茶の本』にみる「反逆」と道教との関連性/2 島崎藤村と『茶の本』/天心の熱烈な崇拝者として/島崎藤村とライトの「家」/3 ハーンへの思慕/ハーンの義 的なペン/ハーンを尊敬していた天心/4 アジアへのまなざし/アーノルド『アジアの光』/悲母観音と『アジアの光』/5 「道」を極める/『武士道』と死の術/道は技より進めり/ヨネ・ノグチと『茶の本』/茶道の思想──戦後期の『茶の湯文学』と映画/6 インドという立脚点/ニヴェディタ『インド生活の綾』/ニヴェディタと天心の出会い/ロマン・ロランが見たマクラウド/ヒンドゥー教(インド教)と仏教の混淆/観音は男性だった?/天心の「戯れ歌」/7 日本における茶の歴史/『茶』史の発展段階と時代精神/『東洋の理想』における雪舟、『茶の本』における雪村/足利時代の風流/第四章 中国文化との関連/1 中国文化・思想への強い関心/風光明媚にして「茶旨し」/老子と青龍/黄帝/2 詩や寓話、玉をめぐって/自然派の詩人・屈原/北京白雲観での「修行」/中国の玉(翡翠)/「三聖吸酸」/第五章 万国博覧会と日本の建造物/1 万国博覧会(一八七六~一九〇四)と日米文化交流/経済と文化(ジャポニスム)の緊密な関係/フィラデルフィア万博に魅了されたフェノロサ/陶芸コレクター・鑑定家としてのモース/ニューオリンズ万博とハーン/2 シカゴ万博と鳳凰殿/エクステリアとジャポニスム/フィラデルフィア万博とフランク・ロイド・ライト/天心が考えた「鳳凰殿」/シカゴ万博のティーハウス(茶館)/フリーアと鳳凰殿/第六章 ガードナー夫人のサロンに集う人々/1 少女イザベラの夢/「ボストン・ブラーミン」の人脈/グリーン・ヒルのガードナー邸での「茶会」/天心がガードナー夫人に贈った茶道具/2 天心とガードナー夫人の十年間(一九〇四~一九一三)/天心とガードナー夫人の出会い/ガードナー夫人の〝お気に入り〟/ガードナー夫人の肖像画/ベレンソンとガードナー夫人の書簡/ゲスト・ブックは語る/3 充実した日々と突然の別れ/「私の今年の夏はいつもとは違っています」/放浪者と迷子のためのクリスマス晩餐会/フェンウェイ・コートにおける厳粛な茶会/プリチャードによる追悼/贈り物のやりとり/第七章 詩で詠む『茶の本』の世界/1 天心が愛した東洋の詩人たち/詩人哲学者と国民的英雄/詩人の三条件──直観力・鋭敏性・躍動感/不羈独立のスイス/ヨーロッパの国民的英雄を「発見」/ウィリアム・テルを讃えて/鈴木大拙「タゴール氏につきて思ふこと」/花を愛でた文人たち/杜甫・白楽天とのかかわり/ベルクソン・九鬼周造と坂本龍一/詩と押韻──韻律へのこだわり/九鬼周造の「粋」とは?/2 プリヤンバダ・デーヴィーと『茶の本』/詩人プリヤンバダ・デーヴィー夫人と天心の出会い/In appreciation of The Book of Tea──『茶の本』を称えて/玉樹──相聞歌のはじまり/生きた蝶と標本の蝶──Dear Mr. Okakura宛て/プラモナウト・チヤウドリの『茶の本』献辞/3 ミショーのアジアについての見解/ハイレベルなベンガルの詩人たち/インドにおける偶像崇拝/老子の文体/4 タゴールと日本文化/ノーベル賞作家タゴールの訪日/タゴールが感服した芭蕉の俳句/ベンガル民衆に敬愛されるタゴール/5 ヨネ・ノグチと谷川徹三/ヨネ・ノグチの日本詩歌論/タゴールに救われたハンセン病患者・志樹逸馬/日英文化交流をめぐって/知られざる詩人哲学者・谷川徹三と『茶の本』/6 白秋と天心/北原白秋と『赤い鳥』/『茶の本』と「歌を忘れたカナリア」/終章 黄昏/1 天心の二重の人生──2 lives/What prospects──美を探索する者/『ウパニシャッド』に見る2 lives/2 プリヤンバダ・デーヴィー夫人との相聞歌/三通目の「奥様」宛(一九一二年一二月三日)/海辺の思い(一九一三年四月二九日)/「黄昏漂いくる芳香なる人へ」(五月四日)/「名前なき名の君なる人へ」(五月八日)/「水の中の月なる人へ」(五月一七日)/「無数の名前なる人へ」(五月二五日)/花の章を話題に(六月一三日)/プリヤンバダ、タゴールが天心に捧げた追慕/天心の辞世/あとがき/資料・参考文献──『茶の本』の世界を深めるために
感想・レビュー
-
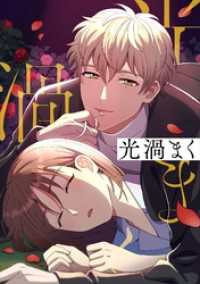
- 電子書籍
- 光渦まく【タテヨミ】9話
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】夜伽が禁忌のこの世界で【…
-

- 電子書籍
- 目覚めたら悪女でした【タテヨミ】第20…
-
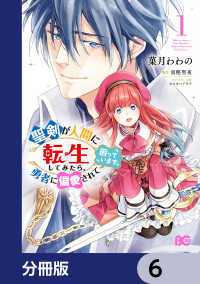
- 電子書籍
- 聖剣が人間に転生してみたら、勇者に偏愛…
-
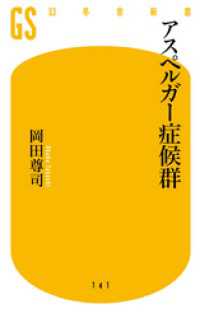
- 電子書籍
- アスペルガー症候群 幻冬舎新書




