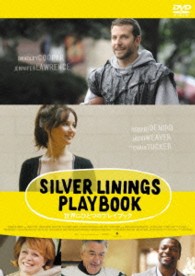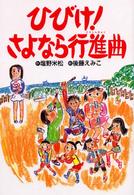内容説明
佐倉藩士として生まれた津田仙は、幕府通詞として福沢諭吉らとともにアメリカへ派遣されるなど将来を目されたものの、幕府瓦解後は農村改革を夢見るにとどまっていた。黒田清隆のもとで働く中、女子留学生を渡米させる計画を聞いた仙は、わずか6歳の娘・梅子を推薦する。日本初の女子留学生として、最年少で渡米した梅子だったが、17歳で帰国した時、彼女は日本語さえ忘れていた――。日米の文化の違いや周囲との軋轢、父との葛藤に悩みながら、女子教育のために直向きに歩みを進めた津田梅子の生涯を描いた感動作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かすみ
3
二度目の留学についても、もっと知りたかったなあ。他にも読めばわかるかな?梅がどこで自信を取り戻したのか、おたまじゃくしがカエルになるのはどうして、を教えてあげることはできたのか、わかるエピソードがあったらとても嬉しい。そして最後、手提げ袋の刺繍について父娘で話す場面がめちゃくちゃ良かった。許せなかったことをすべて水に流せたわけではないだろう、時間が解決してくれないこともあるだろう、ただ二人の願いは、互いの存在なくしては叶わなかったと思うと、再び寄り添えた父娘は幸せに見える。2024/07/13
室田 尚子
1
津田梅子と彼女の父親の物語。数えで8歳でアメリカに留学したことは知っていたが、いちばん過酷だったのは帰国した後だったことには思い至らなかった。明治時代、アメリカに10年以上いて日本語が話せなくなってしまった「女性」がどんな扱いを受けたかは想像にあまりある。彼女と共に留学した女性たちは皆、それを耐えながら自分の道を切り拓いていく。その道は一様ではないけれど、それぞれにj近代日本の女性史に大きな一歩だったのだと思う。2025/06/07
たか
1
津田梅子の事が知りたかったのと、植松三十里さんの作品だから読みたいと思って手に取った一冊。 6歳で親元を離れて留学するのは誰にでもできることではないけれど、凡人の自分からみたら 誰もができることではないビックチャンスが巡ってくる運命がちょっと羨ましくもあった。事をなす人はそれなりの環境に生まれているのかなって。 2024/11/15
Y...
1
タイトルの意味は津田梅子と父の仙でした。梅子は父の願いで6歳から11年間をアメリカ留学。帰国後は幼年から長くアメリカで過ごした影響から日本語を忘れて話せなくなった苦労や英語を活かせる思うような仕事が見つからずに悩みながら模索してアメリカの大学に再度学びに行くなど後の津田塾大学の創始者となる梅子の源になってると思った。また2022年に「津田梅子〜お札になった留学生〜」というドラマを観ていたのでイメージが少し役に立ちました。2024/05/22
-
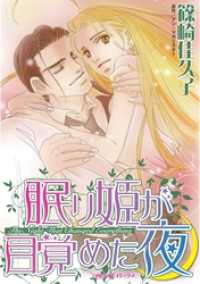
- 電子書籍
- 眠り姫が目覚めた夜【分冊】 5巻 ハー…